第1章:AIが描く「美」と人間が感じる「美」
最近よく耳にするのが、「もうAIでいいじゃん」という声。
デザイン、イラスト、文章、音楽…AIは今、あらゆるクリエイティブ領域で人間の表現を凌駕するスピードと精度を見せている。
実際に、MidjourneyやDALL·EなどのAI生成ツールでは、一昔前では想像もできなかったほど洗練されたビジュアルが一瞬で出来上がる。
僕もプロのデザイナーとして正直驚いたし、ワクワクした。
でも、ふとこう思ったんです。
「じゃあ、僕たち人間の“センス”って、もういらんの?」
そんな時代に、僕たちは何を武器にして生き残るのか?
この記事では、「センス」とは何か、そして*AI時代における“美意識の再定義”*について、僕なりの視点で掘り下げてみたいと思います。
第2章:そもそも「センス」とは何か?
「センス」という言葉、抽象的すぎて正体がよく分からない。
でも実は、センスには“正体”があります。
センス = 知覚のフィルター × 蓄積された経験
- 何を見るか
- どこに違和感を持つか
- どう直したいと思うか
これらはすべて、**“脳内に蓄積された知覚データベース”**に依存してるんです。
要するに、センスは「感覚的な経験則」の集積であり、「見抜く力」「選ぶ力」「配置する力」が複合的に絡み合っている状態。
じゃけえ、センスは「生まれつきの才能」じゃない。
**鍛えることができる“思考の筋トレ”**なんよ。
第3章:AIの美は“平均化された美”
AIが生成するデザインって、どこか整っていて綺麗。
でも、どこか「予想の範囲内」だったり「既視感」があったりしないでしょうか?
それはなぜか?
AIが学習しているのは、過去に人間が生み出した大量の“美のデータ”。
だから、そこから導き出されるアウトプットは、**“最大公約数的な美しさ”**になりがちなんです。
これはつまり、「最大公約数の美」はつくれても、「最小公倍数の感動」は生めないということ。
人間のセンスがすごいのは、
「他の誰も気づかなかった“微差”に気づく力」や「違和感に対して意識的に抗う選択」ができる点です。
第4章:センスとは「違和感を選ぶ力」
ここで面白い話をひとつ。
ある有名なファッションデザイナーは、
「完璧すぎるものは嘘っぽい。1箇所だけ“違和感”を入れるようにしている」と語っていました。
これはまさに、AIには難しい領域です。
AIは最適化・平均化・正解化を得意とする。
でも人間は、そこに**“不完全な魅力”や“ノイズの美しさ”を見出すことができる生き物**なんよ。
- 少しズレた配置
- 不釣り合いな色彩
- 型破りな構図
こういった「意図的な逸脱」は、見る人の脳に引っかかりを生み、“記憶に残る”という価値を創る。
第5章:「感性 × 意図」= 人間にしかできない仕事
ここで大事になってくるのが、“意図”という概念。
AIは、指示された範囲内で最適なものを出すのは得意。
でも、その「そもそも何を創るか」「なぜそれを創るのか」といった問いの立て方は、まだまだ人間の領域です。
つまり、
「意図のないセンス」も「センスのない意図」も、どちらも不完全。
人間が発揮すべきセンスとは、
単なる見た目の良し悪しではなく、**意図を可視化するための“翻訳能力”**だと僕は思います。
第6章:センスは「選びと捨て」の連続
デザインに限らず、あらゆるアウトプットは「選択の連続」です。
- どの情報を見せるか?
- どの要素を捨てるか?
- どの順序で並べるか?
この“取捨選択”のひとつひとつに、人間のセンスが問われます。
AIは提案してくれる。大量に。それも爆速で。
でも、そこから**「どれを使うか?」を選ぶのは人間の役目**なんよ。
ここで重要になるのが、
「誰のためのアウトプットか?」という問いを持つこと。
センスは、“他者視点”があってこそ磨かれるんじゃと思う。
第7章:AI × センスのハイブリッドで未来を拓く
「AIに仕事を奪われる」とよく言われるけど、
僕は**AIは“奪う存在”じゃなく、“増幅させる存在”**だと思っています。
人間のセンスがあるからこそ、
AIの提案も“活きる”し、“跳ねる”。
逆に、人間がセンスを捨てたら、
AIにすら「選んでもらえない」未来が来るかもしれません。
だからこそ僕たちは、
「センスという筋肉」を鍛え続けなきゃいけんのんよ。
- 観察力
- 違和感への敏感さ
- 文脈を読む力
こうした“人間だけが持つ知覚の鋭さ”を磨いてこそ、
AIとの共創が成立すると僕は信じています。
第8章:「センスを鍛える」ための習慣とは?
AI時代を生きる僕たちが、
“人間ならではのセンス”をどう磨いていくべきか?
ここからは実践的なアプローチをいくつか紹介します。
1. 「意図」をもってアウトプットする癖をつける
ただ「なんとなくカッコいい」ではなく、
「なぜこの構成にしたか?」
「なぜこの余白を選んだのか?」
言語化できるレベルまで、自分の選択を掘り下げてみる。
これが“再現性のあるセンス”を育てる基本やね。
2. 「観察眼」を鍛える
普段から街中の看板、広告、UIなどを見るときに、
- なんでこの色なんじゃろ?
- この配置、情報がスッと入ってくる理由って?
- 逆に、なぜこのデザインは読みにくいんじゃろ?
…みたいに、“理由を考える癖”を持つこと。
観察する力は、センスの土台になるよ。
3. 「違和感を放置しない」
「なんか気持ち悪い」「なんかしっくりこない」
──この“なんか”を言語化する練習が大事。
そこにこそ、センスの種がある。
第9章:AIと“共鳴”できるクリエイターであれ
これからの時代、
「AIに仕事を奪われる人」と「AIと仕事を創る人」が、
はっきり分かれてくると思います。
前者は、センスや判断をAI任せにする人。
後者は、AIを相棒にしてアウトプットの質を上げていく人。
AIが爆速で10案出してくれるなら、
僕たちはその中から**「最も伝わる1案」を見抜く目**を鍛える必要がある。
第10章:人間の“センス”が生きる場所は、これからも残る
いくら技術が進化しても、
「感動」や「共感」っていうのは、やっぱり人間の感情の領域。
数字では測れない、でも確かに存在する「余白の美」や「間の妙」。
そういう領域こそが、人間のセンスの真骨頂やと思う。
結局、誰かの心を動かすのは、
**どこまでいっても“人間の意図”と“人間の感性”**なんよね。
おわりに:センスは「武器」ではなく「言語」である
最後に僕が伝えたいのは、
センスって「才能」じゃなくて、「言語」なんじゃってこと。
学び、鍛え、磨くことができる。
そして、**AI時代においてこそ、より価値を持つ“言語”**になる。
だからこそ、
“人間のセンスはもう要らない”なんて言わせないためにも、
ウチらクリエイターは“感性を言語化する力”を磨き続けていこうじゃないですか。
💬「センスが伝わるデザインにしたい」そんな相談、受け付けています。
AI時代のデザイン、どうすれば伝わるのか?
センスってどうやって鍛えるのか?
そんな悩みに、デザイン視点+脳科学・心理学ベースの知見からお応えします。
気軽に相談してみてくださいね!

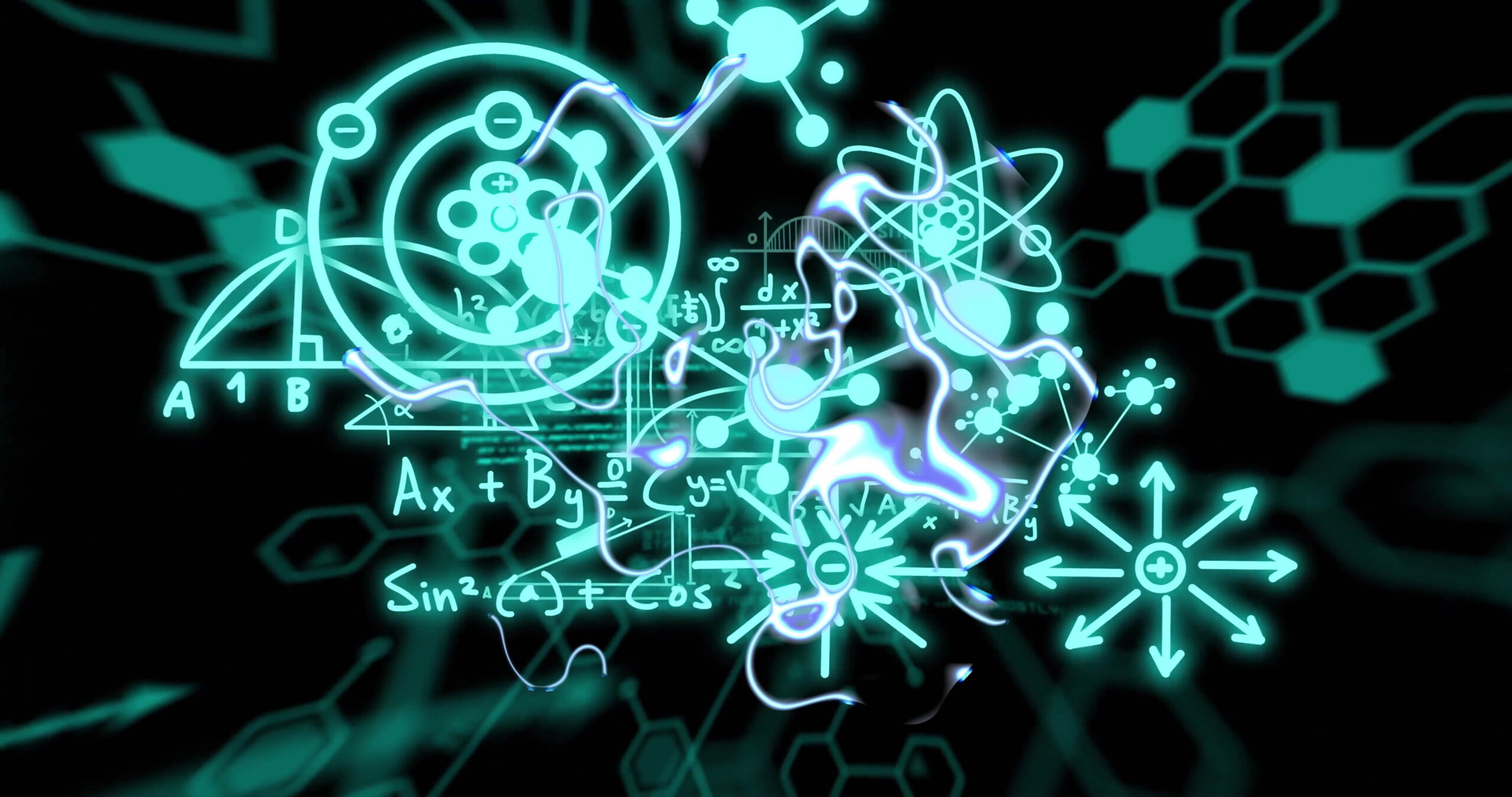


コメント