第1章:なぜ「AI活用」が上手くいかないのか?
ここ最近、「AI使ってるけど、あんまり役立ってないんよね…」という声をよく聞くようになりました。
でも、それって本当に「AIのせい」なんでしょうか?
多くの場合、その裏にはAIリテラシーの格差が隠れていると僕は感じています。
ツールとしてのAIの性能はすでに凄まじいレベルに達していますが、それを「道具」として使いこなせるかどうかは、使う側の力量に大きく依存するようになってきました。
たとえば、ペンタブを与えられても絵が描けない人がいるように。
高級な包丁を持っていても、料理の腕がなければ意味がないのと同じです。
問題は「AIそのもの」じゃなくて、AIを使いこなす“問いの力”が足りてないことなんです。
第2章:「AIリテラシー」はスキルではなく思考の深さ
「AIリテラシー」と聞くと、
「プロンプトエンジニアリング」や「ツールの操作スキル」を思い浮かべる人が多いかもしれません。
確かにそれも大事なんですが、本質はそこじゃないと僕は思っています。
本当に重要なのは、
“問いを立てられるか?”
ということ。
言い換えると、「そもそも、AIに何を聞くのか?」っていう部分です。
これがズレてると、どれだけ高性能なAIでも、見当違いな答えを返してきます。
つまり、AIに正しい答えを出させるためには、こちらが正しい“問い”を投げられるかどうかがすべてなんです。
第3章:AI活用における“問い”の設計力
僕の周囲には、AIを爆速で使いこなしている人たちがいます。
彼らの共通点は、「問いの設計」がめちゃくちゃ上手いということ。
- 課題の構造を把握して
- ゴールから逆算して
- 必要な情報を段階的に引き出す
この3ステップを自然にやっているんです。
たとえば、「新規事業のアイデアを出したい」ときでも、
- まず市場の構造を聞く
- 競合の傾向を調べる
- ペルソナを仮定して、そのペルソナ向けのニーズを掘る
- そこから価値提供の角度を組み立てる
っていうふうに、AIに“考えさせる順番”を与えてるんですよね。
これはまさに「問いを使って、AIの頭脳をナビゲートしている」状態。
逆に、「AIに全部考えてもらおう」として丸投げすると、残念ながら中身スカスカのテンプレ回答が返ってきます。
第4章:リテラシーの“壁”が分断を生む
ここに、深刻な分断が生まれ始めています。
- AIを“答え製造機”と勘違いして使ってる人
- AIを“思考の加速装置”として活用してる人
この2者のあいだには、思考スピードもアウトプットの質も大きな差があります。
そして、これは単なる「スキルの差」ではなく、思考の構造の差なんです。
つまり、AIリテラシーとは「操作力」ではなく「問い力」である。
この前提を間違えると、いつまで経ってもAIは“使えないツール”のままです。
第5章:AIは「答え」ではなく「問い」の共犯者である
さて、ここでちょっと視点を変えてみましょう。
僕がよく思うのは、AIは「答えを出してくれるもの」じゃなくて、「問いを磨くための相棒」やと思った方がええってこと。
ChatGPTやGeminiを使う人たちの間で、圧倒的な差を生むのは「質問力」──つまり、どんな問いを立てるかなんよ。
ただ聞くだけの人 vs. 質問をデザインする人
たとえば、「おすすめの本教えて」って聞くのと、
「30代前半のマーケティング志望の人に向けて、ストーリーテリングの重要性が感覚的に伝わるような本を3冊教えて。できれば読みやすくて、事例が多いものがいい。」
って聞くのとでは、AIが返してくる情報の精度と質がまるで違うんよ。
僕の感覚やけど、**AI時代の知性って、“問いを組み立てられる力”**なんじゃないかと思う。
AIは無限に知識を持ってるけど、それをどう引き出すかは「人間の問い」にかかってる。
つまり、「問いの質=アウトプットの質」なんよね。
第6章:「考えること」と「問いを持つこと」の違い
ちょっと哲学的な話になるけど、「考える」って行為と、「問いを立てる」って行為には明確な違いがある。
「考える」は、すでに与えられた問いに対して答えを出そうとする行為。
一方で「問いを立てる」は、自分でフレームを創ることやと思う。
この「フレームを創る力」こそが、AIが絶対に真似できない部分で、
これができる人は、どんなAIを前にしても使い倒せるし、
これができない人は、いくら高性能なAIを持ってても**“賢くなれない”**んよな。
たとえば、こういう人いません?
- 「AIに聞いたらええやん」って言うけど、聞き方が雑すぎて出てくる答えが微妙
- 「答えが合ってるかどうか不安」っていつまでも疑って、結局動かない
- 「AIに仕事を奪われる…」と脅されてるけど、そもそもAI使ってない
このタイプの人に足りてないのは、「問いの力」なんよ。
つまり、「自分の頭で問題を定義しなおす力」ってこと。
第7章:リテラシー格差は、“問い格差”でもある
じゃあ、なんでこんなにもAIの使い方に差が出るのか?
それは単なる**技術格差(使える/使えない)**じゃなくて、問い格差が根本にあると思う。
AIが出す答えを鵜呑みにする人と、
AIを“思考の相棒”として活用する人では、人生レベルで分岐点が生まれる。
たとえば、
- マーケターがAIにアイデアを出させる
- ライターが構成をAIに手伝わせる
- デザイナーがキャッチコピーの候補をAIに出させてブラッシュアップする
これ、全部**「問いの力」次第で結果が変わる**。
しかもおもろいのが、問いって「思考の解像度」が上がるほど、どんどん磨かれていくんよな。
つまり、AIを使い込めば使い込むほど、問いの質も自分の頭の回転も上がっていく。
逆に、使わん人はずっと「答えを待つだけの人間」で止まってしまう。
ここに、致命的なリテラシー格差が生まれてるってワケ。
第8章:AI時代に必要なのは、「問いを持つ勇気」
AI時代における本質的な差は、**「問いの質」**に表れます。
情報の海で泳ぐのではなく、「なぜそれを知りたいのか」「どこに活かしたいのか」「どういう視点で見るべきか」といった、自分だけの“問い”を立てられるかが決定的な差になります。
「AIに使われる人」と「AIを使いこなす人」の違いはここにある、と僕は思ってます。
- 「正しい使い方を教えてください」と言う人は、AIに依存しがち。
- 「こんな使い方できるかな?」と自分から問いを立てる人は、AIと共創できる。
リテラシーの差とは、「使い方を知っているか」ではなく、「問いが立てられるか」にシフトしてきています。
つまり、知識よりも「意図と思考力」の時代なんよ。
「問いを鍛える」ためにできること
じゃあ、問いの力をどう鍛えるのか?
僕がオススメするのは、以下の3つ:
- インプットを“批評的視点”で見ること
→ 「これは本当に正しいのか?」「別の視点は?」と疑ってみる癖をつける。 - AIに“質問”ではなく“命令文”を与えてみること
→ 「こういう背景があって、こういう条件のもと、こういう目的でこの文章を書いて」と、自分の頭の中を言語化する練習になる。 - 問いメモ習慣を持つこと
→ 普段の仕事や生活の中で、「あれ?なんでこれってこうなん?」と思った瞬間をメモする。これが思考の種になります。
おわりに:「AI×問い」で、自分の思考を武器にしよう
AIは、決して“敵”ではないし、“魔法の杖”でもない。
ただの道具や。しかも、かなり優秀な。
でも、「優秀な道具」を“使いこなせるか”どうかは、結局その人次第なんよね。
時代のスピードが上がって、技術が暴走しそうな中で、僕ら人間が持つ一番の武器は「問いを持つこと」。
問いがある限り、考えることを放棄せん限り、僕らはどこまでも進化できる。
AIと一緒に、やけどな。
デザインの思考も「問い」から始まる
この記事を読んで、「問いを立てる力って面白いかも」と感じた人。
それ、デザインの力にも直結してます。
「どうすればもっと伝わるんか?」
「ユーザーが思わず動きたくなる見せ方って?」
「ブランドの“らしさ”って、何色で表現できるんやろ?」
こうした問いは、全部デザインの仕事です。
僕は、そういう「問いベース」のデザインの相談に乗っとるよ。
もし、今何かデザインで悩んでることがあれば、気軽に相談してみてください。
小さな違和感から、大きなブランディングまで、問いを掘るお手伝いをします。
👇こちらからどうぞ
デザイン相談フォームはこちら


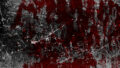

コメント