第1章:美しさの“ズレ”に人は惹かれる
僕らデザイナーがつい陥りがちなのが、「正解を作ろう」とする癖です。
整っていて、バランスが取れていて、色彩も調和している──そんな完璧さを目指すあまり、どこか印象に残らない、平凡なデザインになってしまうことがあります。
でも、ここ最近のデザインの潮流を見ていると、それとは真逆の動きが増えてきました。
むしろ“ちょっとズレてる”とか、“なんか気持ち悪い”くらいのバランスの方が目を引く。
パッと見て「なんだこれ?」とスクロールの手が止まる。それが今の“違和感ドリブン”のトレンドです。
これは一種の「アンチルール」デザイン。
既存のルールやセオリーを、あえて崩す。
その「わざとっぽさ」が、今の時代にフィットしているように感じます。
かつてのトレンドは“完成度”でした。
でも今は“未完成感”とか“崩し”の方が、感性に刺さる。
なぜそうなってきたのか。
なぜ“崩れている”ものが今の人の心を動かすのか──。
この記事ではその理由を解き明かしつつ、実際にどんな表現が「今っぽい違和感」として機能しているのかを深掘りしていきます。
第2章:ルール疲れと“ほつれ”の快感
「アンチルール」が注目される背景には、社会全体の“ルール疲れ”があるように思います。
たとえばSNSでは、ルールやマナー、常識が毎日どこかで論争になっています。
「こうあるべき」「それはマナー違反」と、正しさが溢れすぎて、息が詰まりそうになることもありますよね。
そういう息苦しさのなかで、“わざとズラす”とか“ルールを無視してみる”という行為には、ちょっとした快感があります。
まるで、ピシッと張ったシャツのボタンを一つ外すような。
きっちりと折りたたまれた布を、少しだけくしゃっと崩してみるような。
デザインも同じで、「整いすぎた世界」に慣れた目には、“ちょっとしたほつれ”が逆に魅力的に映るんです。
これを心理学的に見ると、“適応疲労”や“刺激飽和”といった言葉が当てはまります。
人は、あまりにも正しすぎる情報には慣れてしまい、反応しなくなります。
だから、「え?なんでここだけずれてるの?」というポイントに、脳が勝手に反応してしまう。
これはまさに「コントラスト」や「違和感」がトリガーになるという、デザインの基本原則の応用でもあります。
第3章:“ズラし”をどうデザインに落とし込むか
とはいえ、ただルールを無視すればいいわけではありません。
むしろ、“ズラし”や“崩し”のバランス感覚こそが、今のデザインに求められるセンスです。
ここでは、いくつかの「アンチルール的デザイン」の具体例をご紹介します。
1. あえての余白崩し
余白はデザインの命。だけど、あえて片側だけギュッと詰めてみたり、上下左右で非対称な配置にすると、一気に“違和感”が生まれます。
2. タイポグラフィの歪み
整ったフォントだけで構成された画面よりも、あえて手書き風や崩し系フォントを混ぜることで、感情的な揺らぎが生まれます。
3. “ズレ”た動き
アニメーションやスクロールの動きを、ほんの少しだけタイミングをズラすことで、妙な“人間くささ”やクセが生まれ、印象に残る演出になります。
4. ハズした配色
補色やトーンをわざとぶつけたり、目がチカチカするようなカラーリングを“部分的に”使うことで、“ちょっと気になる”仕掛けになります。
これらの“ズレ”を成立させるために大事なのは、全体のコンセプトやメッセージとの整合性です。
「わざとやってる」と伝わるようにするには、他の部分の完成度や統一感をしっかり保つ必要があるんですよね。
第4章:「ルール違反」にこそ生まれる熱狂と中毒性
「違和感」が与える印象には、単なる目立ちや奇抜さを超えた力があります。それは“中毒性”です。
これ、言い換えれば「わざと外してる」からこそ、“なぜ?”と脳に問いかけが生まれる構造。つまり「意味を探したくなる」。
たとえば、左右非対称のレイアウトや、整ってない文字組、1色だけ異様に浮いているカラー…
普通に見たら「これミスなんじゃない?」ってツッコミたくなる。でも、そこに“明確な意図”があった場合、それは一気に「センス」へと変わります。
これは「アノマリ効果」と呼ばれる心理学の原理でも説明できる現象で、人は「パターンから外れた要素」に自然と注目する傾向があります。
つまり、ずっと整ってるデザインの中に、意図的な“崩し”を一つだけ入れることで、視線を集中させ、印象に強く残すことができるというわけです。
しかも今の時代、「整ってる」よりも「覚えてる」ほうが価値が高い。
それってつまり「整ってる=正解」という前提自体が揺らいでいる証拠なんじゃないかなと思うんです。
第5章:「違和感デザイン」は誰でもできるのか?
じゃあ、「違和感デザイン」は誰でもできるのか?って話ですが、僕は「できる」と思ってます、条件付きで。
その条件っていうのが、「ルールを理解したうえで壊してること」。
つまり、ルールを知らずに壊すとただの事故。ルールを知った上で壊すとアートになる。
これはファッションでも音楽でも一緒です。
音楽理論を熟知した上で崩すから“ジャズ”が成立するし、ドレスコードを理解した上で外すから“おしゃれ”になる。
逆に言えば、ベースに「基本設計の美学」がある人がやるからこそ、“違和感”が価値になるんよ。
ただ単に崩すだけじゃ、伝わらんし、意味も生まれない。
この「意味を持たせる崩し方」を身につけるには、やっぱり“良い崩し”をたくさん見ることが大事です。
参考になるのは、アートディレクションに尖ったブランドやアート系プロジェクト、海外の雑誌系デザインなど。
▼たとえばこんな感じのスタイルが参考になります:
- Brutalist Web Design
- Anti-design movement(ヨーロッパ圏)
- Zineカルチャーに近いグラフィック系
あと、ギャラリーサイトでいうと Mindsparkle Mag や siteinspire なんかも、こうした尖ったデザインが多くておすすめ。
第6章:「整える」か「崩す」か──その判断軸とは?
さて、「整えるか」「崩すか」の判断ってどこですればいいんでしょう?
これ、僕的には「目的」しかないと思う。
つまり、“誰に何を伝えるか”が明確になれば、自然と「整えるべきか」「崩すべきか」が決まる。
●伝えるべきことが複雑で誤解されたくない → 整えた方が良い
●印象を残して記憶に焼き付けたい → 崩した方が強い
特にブランドやアーティスト系の発信では、必ずしも「理解されること」が目的じゃない。
むしろ「理解されなくても惹きつけられる」っていう方向性の方が正解だったりする。
だから、僕が最近よく言うのは、
「読まれなくてもいい。でも“刺され”」
ってやつです。
ぜんぶ伝えなくていい。ただ、1つでも記憶に刺さるなら、それは価値。
そのための「違和感」は、すごく大事な武器になると思ってます。
第7章:それでも「伝わる」は外せない
「アンチルール」や「違和感」を仕掛ける上で、絶対に忘れちゃいけんのが「伝える」っていう本来の目的です。どれだけ尖ったデザインでも、受け手に「何を伝えたいか」がわからんかったら、それはただの自己満足になってしまう。
例えば、フォントを限界まで崩したタイポグラフィポスター。美術館に展示されてる分にはアートとして機能するかもしれんけど、商品の広告やブランドのLPでそれをやってしまったら、読みづらい・伝わらない・離脱される…って結果になるのは目に見えとる。
ここで大事なんは、「崩し方に意図があるかどうか」「その違和感が伝達を妨げてないかどうか」を見極める力なんよね。ウチらデザイナーはアーティストと違って、「伝える」責任がある。伝わらんデザインに価値はない、って言い切ってもええくらいやと思う。
だからこそ、アンチルールや違和感の演出は、「伝わる」を前提にした“戦略的崩し”である必要があるんよ。
第8章:これからのデザイナーに求められる力
これからの時代、「デザイン=きれいに整える」だけじゃ通用せんようになってくる。情報過多で、広告もコンテンツもあふれかえった時代において、整ったデザインなんて当たり前。その上で「おっ?」と思わせる仕掛けがなかったら、まず見てもらえん。
でも、ただ奇抜にすればいいわけでもない。そこには「なぜその崩し方を選んだのか」「どうして違和感を与える必要があるのか」というロジックと意図が絶対に必要。
つまり、これからのデザイナーに求められるのは…
- 視覚表現だけでなく、構造や意味までデザインできること
- 意図的な“違和感”を操作できること
- ルールとアンチルール、どちらも使いこなせるバランス感覚
- 「整える力」と「壊す勇気」を両立させる胆力
この4つやと思う。
AIがデザインを整えてくれる時代やからこそ、「あえて整えない」「壊す」という選択に、人間の感性がより強く求められてくるんよね。
おわりに:違和感は、新しい秩序の入口。
「違和感」っていうのは、じつは「時代が変わろうとしてるサイン」でもあると思います。
常識やルールがガラッと変わる前って、たいてい「それっておかしくない?」っていう違和感が先にやってくるんよね。違和感は、変化の前兆。つまり、違和感を仕掛けるデザインは、次の時代の入口に立つ役目を担ってるとも言える。
僕はこれからも、整えながら壊して、壊しながら整えていく。そうやって“意味ある違和感”を生み出せるデザインを、もっと極めていきたいと思っとる。
💬デザインのご相談はこちらから
「アンチルールを使ったデザインに挑戦してみたい」
「うちのサービスにも“違和感”を取り入れて目立たせたい」
「ただ整えるだけじゃない、本質的なブランド設計を相談したい」
そんなご相談、お気軽にどうぞ。

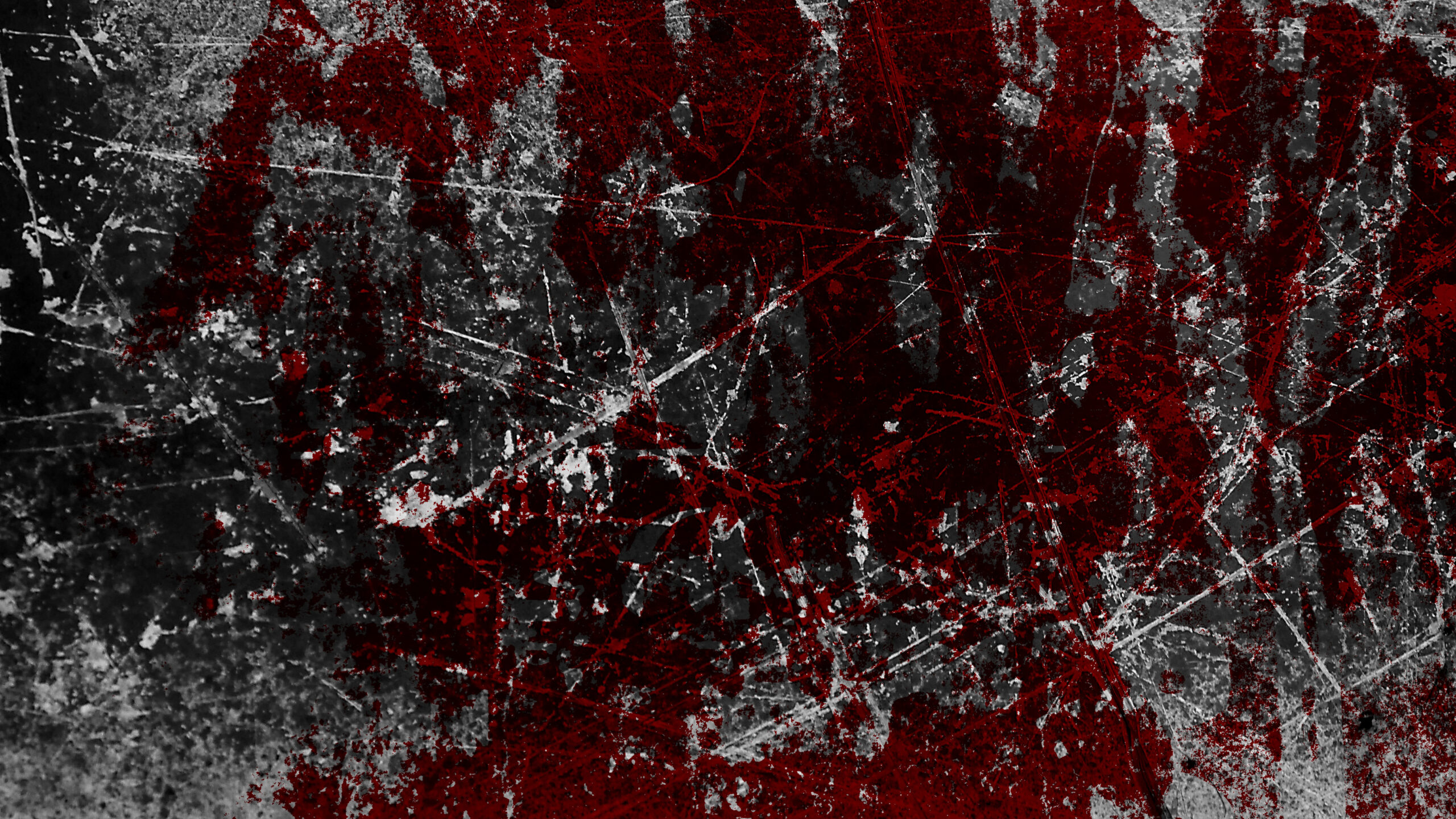


コメント