第1章:デザインって「盛る」もの?それとも「削る」もの?
「デザインってオシャレにすることでしょ?」
そう思われがちですが、現場で長くやっていると真逆の答えにたどり着きます。
むしろ「余計なものを削る」ことのほうが圧倒的に大事なんです。
たとえば、WEBサイトを作るとき。 お客様から「これも伝えたい」「あれも見せたい」という要望をいただくことが多いです。
もちろんその気持ちは分かりますし、全部伝えたい内容なのも理解しています。 でも、全部を詰め込んでしまうと──
- 結局なにが言いたいか分からなくなる
- 見る側が疲れる(読む気なくす)
- 成果につながらない
つまり、「盛れば盛るほど弱くなる」のがデザインの怖いところ。
だからこそ、“引き算”の思考が大事になります。
第2章:情報が多すぎる時代に必要な「削ぎ落とし」
今の時代、情報が多すぎます。
X(旧Twitter)やInstagram、YouTube、LINE… 1日で何十、何百という情報が目に入ってきます。
そんな中で、あなたのデザインが「見られる」「伝わる」ためには、
いかに“余計なもの”を削ぎ落とすか?
これが肝になります。
例えば、次のような質問を自分に投げかけてみましょう:
- この要素、本当に必要?
- これがなくても目的は達成できる?
- それって誰のためにあるの?
こうした“問い”を通して、デザインをスッキリ整理していくのがプロの仕事じゃと思うんです。
第3章:「伝えたいこと」じゃなく「伝わる形」に
よくある間違いが、「伝えたいことを全部盛り込もうとする」ことです。
でも実際には、「伝えたいこと」と「伝わること」は別モノ。
たとえば、こんな経験ないですか?
- 資料を頑張って作ったのに、誰も見てくれなかった
- Instagramの投稿がいまいち反応悪い
- 営業資料を送っても読まれてる感じがしない
それ、実は「伝える順序」や「見せ方」の設計が原因かもしれません。
大切なのは、「伝えたいことを削る勇気」。
そのうえで、「相手に伝わる順序」に並べ替えること。
ここで重要になるのが、「引き算から始める」っていう発想です。
先に減らしてから、構成を立て直す。 これができると、グッと見やすく・伝わりやすくなるんよね。
──というわけで、ここからは引き算デザインの具体的なプロセスに入っていきます!
第4章:情報整理のステップは“足し算”じゃなく“引き算”
僕がデザインで最初にやることは、「何を削るか?」を見極めることです。
これはWebサイトでも、バナーでも、LPでも同じ。
情報の中に「削れるもの」があるかどうかをチェックしてからじゃないと、 どれだけレイアウトや配色を工夫しても意味がありません。
では、どうやって「削る基準」を作ればいいか? ここでは、我々が現場で使っている3つの質問を紹介します。
1. 目的に関係ある?
「この情報、ゴール達成に関係ある?」という問いかけ。 例えば「資料請求してもらいたいLP」で「社長の趣味紹介コーナー」があっても、意味ないですよね。
2. 今このタイミングで必要?
伝える順序ってすごく大事で、「今は言わんでええ」って情報もあります。 あとで詳細ページに回すのもあり。
3. 誰が喜ぶ?
その情報が「作り手」だけが満足する内容なら、思い切って削除。 見る人の“役に立つかどうか”が基準です。
これらを問いながら「本当に必要なもの」だけを残していくと、自然とスッキリしたデザインになります。
第5章:「余白」はデザインじゃなく“配慮”
「引き算の結果、空間が生まれる」 そのとき初めて“余白”が活きてくるんですよね。
デザインって、何かを置くことじゃなく、置かないことにも意味がある。 これは、広島弁で言うたら「おいときゃええゆうもんじゃない」って感じです(笑)
余白があることで:
- 読みやすくなる
- 高級感が出る
- 見る側のストレスが減る
つまり、余白は“優しさ”なんです。
一度、スマホの画面でギチギチのバナーを見てみてください。 「うっ…」ってなった経験、ありますよね?
逆に、余白があってスッキリしたデザインって、それだけで信頼感がある。
この「削る→余白が生まれる→見る人が喜ぶ」って流れは、まさに引き算デザインの醍醐味じゃと思うんよ。
第6章:「削る」ことで伝わるもの
ある意味、「引き算」は勇気がいります。
クライアントさんの要望を削るって、怖いことでもあるし、説明責任も求められます。
でも、それをちゃんと論理で伝えると、意外と納得してくれる方が多いんです。
むしろ、「そこまで考えてくれてたんですね!」って感謝されることも。
だからこそ、削る判断には“軸”が必要なんですよね。
その軸が、さっき紹介した「3つの質問」だったり、 「目的から逆算する」思考だったりします。
一番伝えたいことを“残す”ために、他を削る。
それができると、「ちゃんとしてる」デザインになる。 「なんかオシャレ」じゃなく、「意味がある」状態に仕上がります。
その結果、問い合わせが増えたり、CVRが上がったり── 成果にもつながるデザインになります。
ここまでくると、引き算はただの整理術じゃなく、 成果に直結する武器なんです。
第7章:「引き算」と「付加価値」は両立できる
ここまで「削る」「減らす」「シンプルにする」って話をしてきましたが、 「引き算=手抜き」ではないってことを強調しておきたいです。
むしろ、引き算ができてる人ほど、“意味ある足し算”ができる。
「無駄な要素を削ったからこそ、1個の演出が際立つ」 「情報を減らしたからこそ、キャッチコピーが刺さる」
この“引き算と足し算のバランス感覚”は、まさにデザイナーの腕の見せどころですね。
たとえば我々の案件では、あえて色を抑えたデザインにして、 最後に1つだけネオン系のピンクを入れることで「目が止まる」設計をしたこともあります。
「どこを足して、どこを引くか」 このジャッジができる人が、ほんまに“考えてるデザイナー”なんじゃと思います。
第8章:まとめと、あなたへの提案
この記事では、「引き算から始めるデザイン整理術」というテーマで、
- 引き算が必要な理由
- 何を削ればいいかの判断軸
- 余白がもたらす効果
- 引き算の先にある付加価値
についてお話してきました。
もし今、あなたが「なんかごちゃごちゃする…」「伝わりにくい気がする…」と感じているなら、
いきなり要素を増やすんじゃなく、まずは“減らす”ことから始めてみてください。
その結果、伝えたいことが際立ち、 見る人に“届くデザイン”に近づいていくはずです。
そして──
「自分だけではうまく整理できない」 「何を削ればいいかわからん…」
そんなときは、ぜひ気軽に相談してください。
我々は、「ビジュアル」だけじゃなく、「設計」から一緒に考えるデザイナーです。
「これ、本当に必要ですか?」って、目的から一緒に問い直しながら、 意味のある“引き算”をご提案します。
フォームからのご相談は無料です。お気軽にどうぞ。
【あとがき】
僕も昔は、「これも入れたい」「あれも見せたい」って、足し算ばっかりしてた時期がありました。
でも、それでクライアントさんが迷ってしまったり、 「なんか見づらい…」って言われたりして、初めて気づいたんです。
「あ、これは“伝えたいことが伝わってない”状態なんじゃな」って。
そこからはずっと、「削る」「減らす」っていう勇気を持つようにしてます。
それでも不安になることはあります。 「これ削ってええんかな…」「大事な情報やないんかな…」って。
でも、その不安に向き合いながら「伝えるために削る」という選択をしたとき、 初めてプロのデザイナーとしての矜持が持てた気がします。
あなたのデザインにも、そんな一歩が訪れますように。

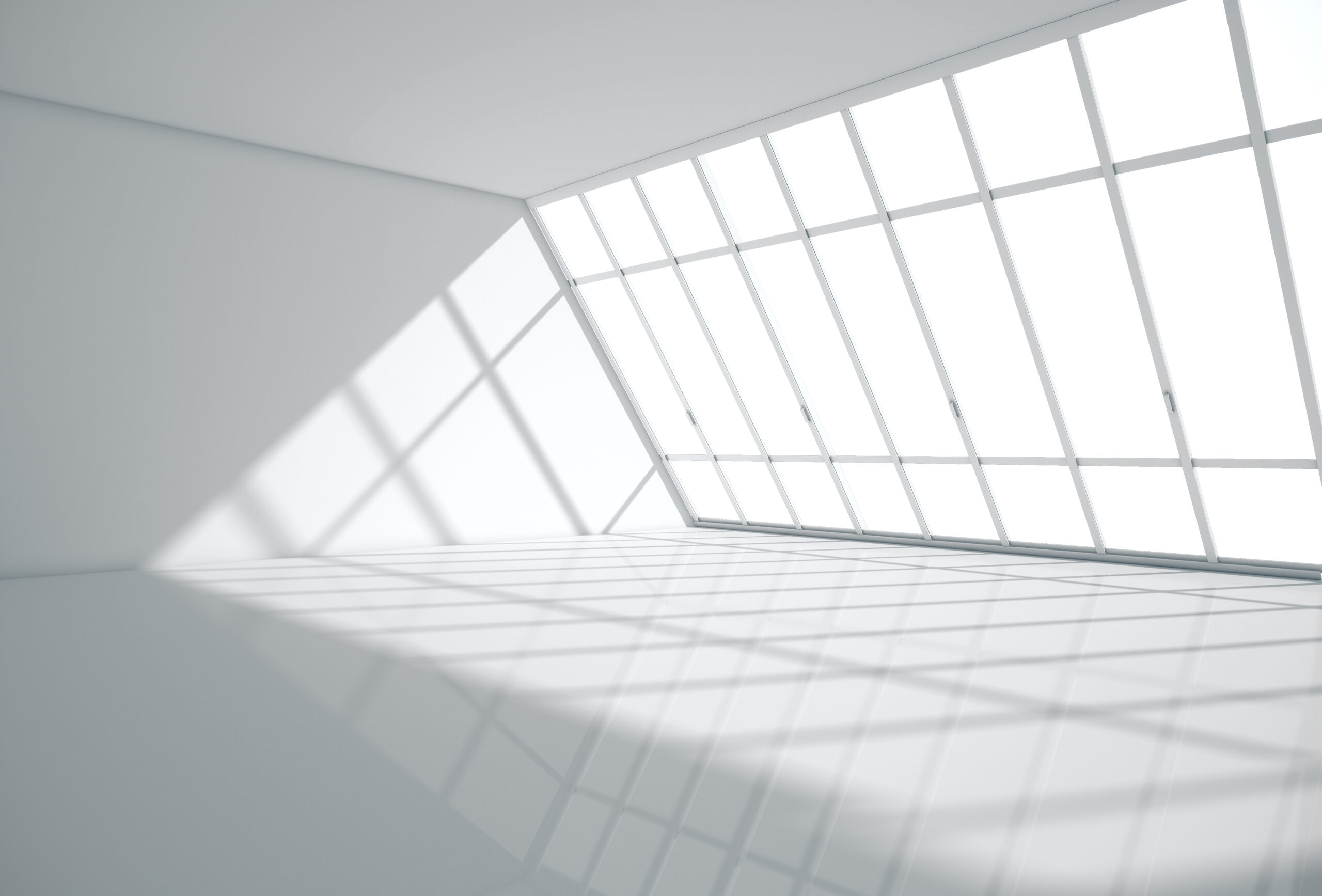


コメント