はじめに:センスがないと配色はムリ?って思ってない?
デザイン初心者にとって、最初の壁のひとつが「配色」かもしれません。
「なんとなく合ってない気がする…」
「全部の色が目立っててゴチャついてる…」
「いい感じにしたいけど、センスがなくて自信がない…」
そんなふうに悩んで、カラーパレット選びに1時間以上悩む。
……僕も昔はそうやったけぇ、気持ちめちゃわかります。
でも安心してください。
配色は「ルール」と「型」さえ知っていれば、センスに頼らずとも安定した仕上がりになります。
この記事では、
「なんとなく」から卒業して、ミスらない配色ができるようになる3つのルールを、
実例と一緒にお伝えします。
センスがなくても、理論でプロっぽい配色はできる!
今日から“色の迷子”を卒業しよう。
第1章:配色は「役割分担」が命 ─ 色にも“仕事”を与えよ
色は「選ぶもの」じゃなくて「働かせるもの」
まず1つめのルール、それは──
「配色には役割を持たせる」こと。
例えば、デザインに3色を使うとしたら、
それぞれにこんな役割を振ってみてください。
- ベースカラー(土台):背景や余白、全体のトーンを支える色
- メインカラー(主役):ロゴやタイトルなど、印象を決定づける色
- アクセントカラー(引き締め):ボタンやリンクなど、視線を誘導したい場所の色
役割を決めてから色を選ぶと、自然とメリハリが生まれます。
逆に、色を“ただなんとなく”選ぶと、視線が定まらず迷子になります。
カラフル=ダメじゃない。でも「秩序」が必要
色数が多くてもOKなんです。
ただし、“秩序”がないと「お祭り騒ぎ」になります。
僕も最初の頃、「色を使いこなす=たくさん色を使うこと」って勘違いしとったんよ。
でもそれってただの“暴走配色”じゃけぇ、見た目の印象が散らかる。
大事なのは、色に「意味」と「役割」があること。
役割ベースの配色例(Webサイトの場合)
| 色の役割 | 色例(青系の場合) | 使用例 |
|---|---|---|
| ベースカラー | #F5F8FA(淡いグレー) | 背景全体 |
| メインカラー | #0077CC(やや明るい青) | ロゴ、タイトル |
| アクセントカラー | #FF6600(オレンジ) | CTAボタン、リンク、強調見出し |
この3色だけでも、シンプルで洗練された印象になります。
第2章:「同じ色味」で揃える ─ トーン管理の鉄則
同系色でまとめると、世界観がブレにくくなる
「色数はそんなに多くないのに、なんかまとまりがない」
そんな時は、トーン(明度・彩度)がバラバラになっていることが原因かも。
色は「赤」「青」などの色相(しきそう)だけじゃなく、
「明るさ」や「鮮やかさ」の差でも印象が大きく変わります。
トーン管理で気をつけたいポイント
- 明度(Brightness):背景や文字の可読性に直結
- 彩度(Saturation):世界観の“濃さ”や“落ち着き”を演出
- 色相(Hue):基本となる色味(赤・青・黄など)
これらがチグハグだと「なんか気持ち悪い」デザインになります。
たとえ配色ツールで選んだとしても、トーンが揃ってないと違和感が出ます。
トーンを揃える具体的な方法
- Adobe ColorやCoolorsなどのツールを使って「同じトーンの色」をピックアップ
- メインカラーを決めたら、その色を元にした明度・彩度違いの色で構成する
- 余裕があれば「トーンマップ(DIC、PCCSなど)」で全体をチェック
第3章:「心理効果」を味方につける ─ 色は無意識に働く
色には、見る人の心に直接働きかける心理的効果があります。
これを知らずに配色すると、知らんうちに“逆効果”になっとることも…。
よく使われる色の心理効果まとめ
| 色 | イメージ | 向いている用途 |
|---|---|---|
| 青 | 信頼感・誠実・安心 | コーポレートサイト、医療系 |
| 赤 | 情熱・行動・注意喚起 | セールバナー、飲食店サイトなど |
| 緑 | 癒し・自然・安らぎ | オーガニック系、美容・健康系 |
| オレンジ | 元気・親しみ・ポジティブ | スタートアップ系、サービス系LPなど |
| 黒 | 高級感・力強さ・洗練 | ブランドサイト、ラグジュアリー系 |
たとえば医療系のサイトで赤を使いすぎると、「不安」「警告」みたいに受け取られるリスクも。
逆に、落ち着いた青や緑は安心感を与えやすく、業種とマッチしやすいんよ。
第4章:配色でありがちなミスとその回避策
さて、ここからは「失敗しがちな配色」について実例とともに深掘りしていきましょう。
ミス①:コントラストが足りない
これは視認性に直結するやつです。たとえば、薄いグレーの背景に薄い青文字とか、白背景に薄い黄色の文字とか…読みづらい!ってやつ。おしゃれに見せたい気持ちは分かるんですが、ユーザーの目線からすると「読むのがしんどい」配色になってしまいます。
解決策:
- カラーコントラスト比を意識すること。
- Webアクセシビリティの基準(WCAG)では、テキストと背景色のコントラスト比は4.5:1以上が推奨されています。
- Google Chromeの拡張機能やFigmaのプラグインなどを使えば、簡単にチェックできます。
ミス②:ブランドカラーを無理やり使いすぎる
ブランドカラーは確かに大切。でも、それを全要素にガンガン使いすぎると、統一感どころか「しつこさ」が際立ってしまいます。強い色を多用すると、見る人の疲労感も高まります。
解決策:
- メインカラーは強調したい1箇所に絞る。
- サブカラーやニュートラルカラーで余白を活かす。
- ブランドカラーの「トーン違い」(淡い色、暗い色)をうまく使う。
ミス③:参考デザインの色をそのまま使ってしまう
これもやりがちです。参考になる海外サイトや有名ブランドの配色をコピペ的に使ってしまうと、文脈や文化の違いで「意味合いがズレる」ことがあります。
たとえば、海外のナチュラル系コスメブランドがよく使っているくすみグリーン系の配色を、日本の中高年向け商品に使ってしまうと、妙に若作りな印象になったりするんです。
解決策:
- 配色の背景にある「意味」「文化的文脈」も意識する。
- 参考にするのは構成や比率であって、色そのものではない。
- 最終的には「誰に何を届けるか」という視点で最適化するのが正解。
第5章:実践的カラーパレットの組み立て方
ここまでで理論を学んだら、次は実践。実際に配色を組む際のプロセスを紹介します。
ステップ①:主役(メインカラー)を決める
まずは主役になる色をひとつ決めましょう。ブランドカラーがあればそれが基本になりますし、商品やサービスのイメージに合わせて選ぶこともあります。
例)信頼感 → 青系、活力 → 赤系、やさしさ → 緑やベージュ系
ここでは「ターゲットの感情を動かす色」を意識するのがポイントです。
ステップ②:脇役(サブカラー)を設定する
メインカラーだけだと単調になります。なので、色相環でいう「類似色」か「反対色(補色)」をサブカラーとして加えます。
- 類似色:まとまりや統一感が出る
- 補色:コントラストが生まれ、メリハリがつく
ステップ③:背景・文字用のニュートラルカラーを決める
最後に、白・黒・グレー・ベージュなどの「ニュートラルカラー」で全体のバランスを整えます。背景や文字、余白などに使われるこの色たちは「主役を引き立てる舞台装置」のような役割を果たします。
ここで失敗すると、どんなに良いメインカラーでも沈んでしまうので要注意。
第6章:プロがよく使う配色ツール&リファレンス
最後に、僕がよく使ってる配色系の便利ツールを紹介しとくね。
1. Adobe Color
色相環を使って、補色・トライアドなどの配色パターンを自動で組んでくれる優れモノ。
https://color.adobe.com/ja/create/color-wheel
2. ColorSpace
ベースカラーを1色入力するだけで、そこからグラデーションやカラーパレットを一瞬で生成してくれる。https://mycolor.space/
3. ColorHexa
カラーコードを入力するだけで、その色に関する詳細な情報(補色・類似色・グラデーション例・カラーブレンド・テキストコントラスト比など)を一気に表示してくれる。
https://www.colorhexa.com/
4. 日本の配色文化に特化した資料
「日本の伝統色」「和の色事典」などの書籍やWebサイトも参考になるよ。特に和風デザインやシニア層向け案件では重宝する。
第7章:配色を武器にする ─ 信頼されるデザイナーになるために
ここまで読んでくださったあなたには、すでに「配色=センス」ではないことが伝わったと思います。
むしろ、配色は「論理」「構造」「文脈」に基づいて判断すべき領域です。
そして、それを一貫性と再現性をもって扱えるようになることが、デザイナーとしての信頼に直結します。
5-1. 「なんとなく」から「説明できる」デザインへ
「なんとなくこの色がいい気がする」
この“なんとなく”を“説明できる言葉”に変換する力こそが、デザインにおける戦略的なスキルです。
たとえば:
- 「このターゲットは20代女性なので、信頼と親しみを与えるためにペールトーンの青系を選びました」
- 「この商品は高価格帯なので、安っぽく見えないよう高彩度・高明度の配色は避けました」
こんなふうに言語化できれば、クライアントからの信頼度も跳ね上がりますし、自分自身の判断にもブレがなくなります。
このフェーズに来た時点で、配色のスキルは“センスの領域”から“ビジネスの武器”に変わってるんよね。
5-2. トレンドを追いかける前に“構造”を理解する
もちろん、トレンドカラーの把握も大事。
だけど、トレンドって一過性のものやし、それだけを追っても意味がない。
大事なんは、「なぜその色が流行っているのか?」という“背景”と“構造”を理解すること。
たとえば「くすみカラー」が流行っているのは、
- 高彩度カラーが多かったSNS時代から、落ち着きや余白感へのシフトが起きてる
- インテリアやライフスタイルもミニマル志向になってきた
みたいな、社会や感性の変化とリンクしてるわけ。
だから「流行ってるから使う」じゃなく、「文脈に合うから選ぶ」って感覚を持つと、トレンドにも振り回されなくなるよ。
おわりに ─ 「色に強いデザイナー」になるために
配色って、確かに奥が深いし、沼にハマると抜け出せなくなる(笑)
でも、僕は「だからこそ面白い」と思うし、
この“構造”を理解した瞬間から、配色は「怖いもの」じゃなくて「使いこなせる武器」になるんよ。
この記事では、配色でミスらないための3つのルールを軸に、
- 配色の“センス頼り”から脱出する方法
- 明度・彩度・色相の「役割理解」
- 色の“意味”と“文脈”の読み解き方
- 実践で活かすための考え方
を丁寧に解説してきました。
「配色が苦手…」「なんかいつも野暮ったくなる…」って悩んでる方には、
ぜひこの考え方を日々の制作に取り入れてほしいです。
きっと、ひとつひとつの色選びに“納得”が生まれるようになるから。
🎨デザインの配色でお悩みの方へ
「自分の配色、本当にこれでいいのか不安…」
「ターゲットに合った色設計ができてるか見てほしい…」
そんな方は、下記のフォームからお気軽にご相談ください👇
あなたの目的・ターゲット・文脈に合った“配色の考え方”を、論理的にアドバイスします!

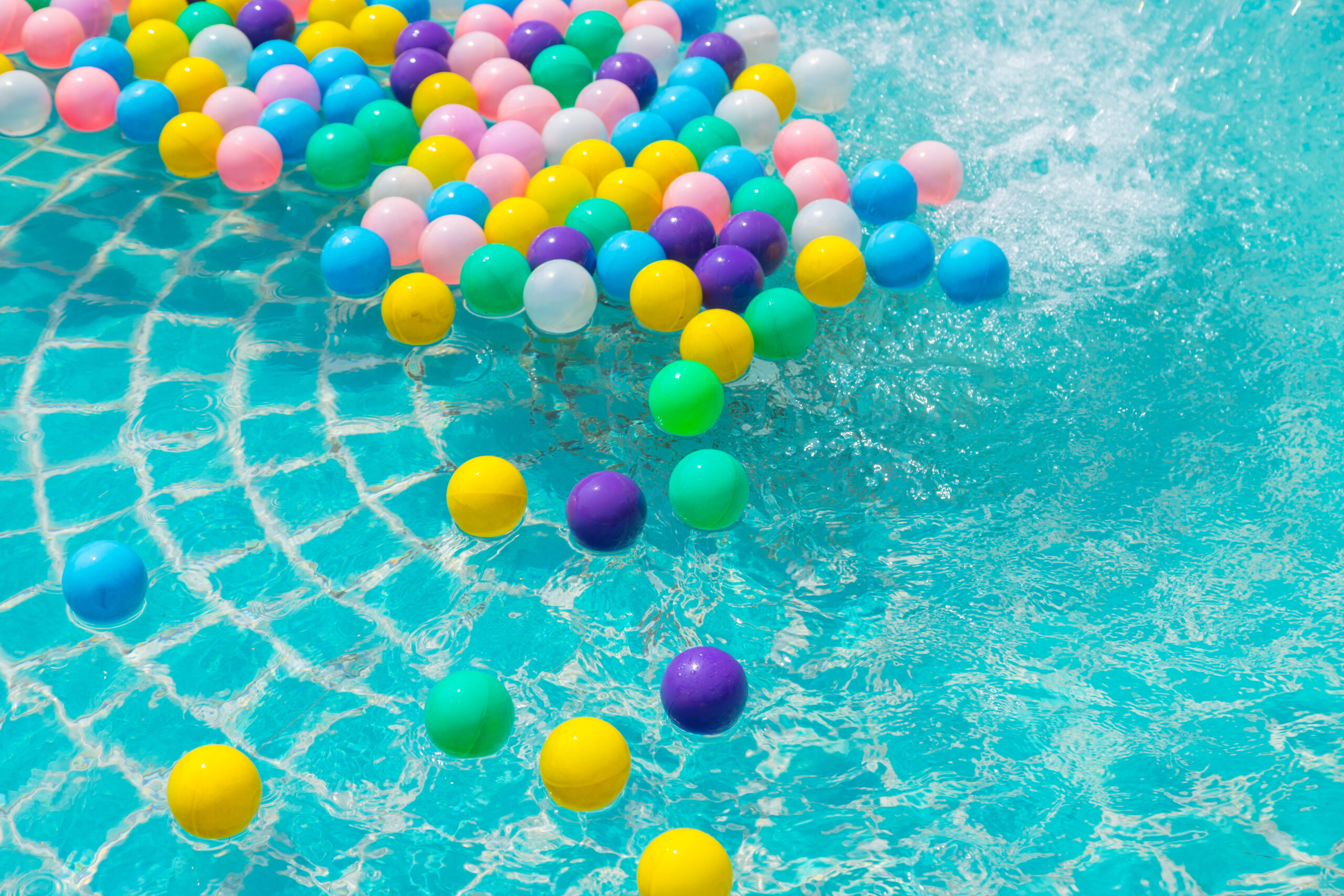


コメント