第1章:ナラティブ・デザインとは何か?
「ナラティブ・デザイン(Narrative Design)」という言葉を、ゲーム業界や体験型コンテンツの分野で耳にしたことがある方もいるかもしれません。
直訳すると「物語の設計」。でも、この言葉がいま、WebやアプリのUI/UX領域でも注目されているのをご存じでしょうか?
ナラティブとは、ただのストーリーではありません。
ストーリーは「起承転結」などの構造を持った語りの形ですが、ナラティブはもっと広義で、「人が意味を見出す体験そのもの」を指します。
つまり、**「ユーザーが、自分自身の文脈で“語れる”体験」**がナラティブ。
ナラティブ・デザインとは、まさにその「語りたくなる体験」を、ユーザーの感情設計や世界観設計を通して丁寧に組み上げていくアプローチです。
たとえば…
- 「サイトを開いた瞬間、なんか世界に吸い込まれた」
- 「スクロールするたびに、なんか映画みたいに展開していく」
- 「自分の物語に寄り添ってくれてる感じがした」
こんな感覚を引き出せたら、もうナラティブ設計の大成功です。
で、ここで大事なのが「ただキレイ」「ただ見やすい」だけでは、もうUX/UIとしては足りないってこと。
いまのデザインには“物語性”が求められてる。
その時代の空気感を、今こそちゃんと捉えるべきなんです。
第2章:なぜ“物語”がUX/UIに必要なのか?
「デザインは課題解決だ」と言われることが多いですよね。
確かにその通りです。でも最近、僕はこう思ってます。
「課題解決だけじゃ、人の心は動かん。」
どんなに機能的に優れていても、どんなに導線設計が優秀でも、人の記憶に残らないデザインって、正直“消費される”だけなんよ。
一方、ナラティブ・デザインを意識したUI/UXには、こんな力が宿ります。
- 没入感を生む:ユーザーが世界観の中に引き込まれる
- 意味づけを強化する:「このサービスは自分に必要だ」と自然に思える
- エモーショナルな共鳴:「なんかわかる」「共感した」という感情の接続
- リテンション(再訪)を高める:思い出として残るから、また使いたくなる
ナラティブって、言い換えれば「ユーザーの物語に寄り添うこと」。
たとえば採用サイトであれば、「この会社で働く自分が想像できた」という体験こそがナラティブだし、ECサイトであれば「このアイテムで日常が変わるかも」とワクワクできる感覚がナラティブです。
つまり、ユーザー自身が“主語”になれる体験をデザインすることが、ナラティブ・デザインの本質なんです。
第3章:「ナラティブ・デザイン」が注目される理由
では、なぜ今この「ナラティブ・デザイン」が注目されているのでしょうか?
その背景には、**「機能性だけでは人は動かなくなった」**という現実があります。
たとえば、かつては「便利だから」「安いから」という理由だけで商品が売れていた時代もありました。でも今は違います。世の中には選択肢が多すぎて、単なる差別化では心が動かないのです。
ここでカギになるのが「物語の力」。
つまり、「このブランドって何のために存在してるんだろう?」「この人が作ってるって知ったら、ちょっと応援したくなった」といった共感や意味づけのストーリーが、無意識に人の判断基準に影響を与えているんですよね。
実際、心理学でも「物語」は記憶に残りやすいことが証明されてますし、マーケティングでも「ヒーローズ・ジャーニー(英雄の旅)」などのストーリーテリング技法は定番となっています。
ナラティブ・デザインは、そういった“物語構造”をUIやUXにまで組み込んで設計するという点で、
単なる「読みやすい」「使いやすい」を超えた情緒的体験の設計とも言えます。
第4章:ナラティブ・デザインの設計手順【実践編】
じゃあ、どうやって「ナラティブ・デザイン」を実装するの?という話。
僕が実際にプロジェクトで使ってるフローを、5ステップで紹介します。
① 主人公を決める(=ユーザーの解像度を爆上げ)
まず最初にやるべきは「この物語の主人公は誰か?」を明確にすること。
つまり、「ユーザーをどれだけリアルにイメージできてるか?」ってことです。
ここが甘いと、どれだけ良いストーリーを書いても「誰に向けた話なん?」ってなる。
ペルソナ設定はもちろん、「この人が今日どんな気持ちでこのサイトを見にきたか?」まで想像しておくと、物語設計に厚みが出ます。
② 現状を描く(=問題提起と共感)
主人公の今の状態──つまり「困ってること」「望んでいること」を明確に描写します。
ここでは、「わかる〜!それ、僕も悩んでたわ」って共感を呼ぶことが大事。
この部分が強いと、その後のストーリー展開への没入感が段違いになります。
③ 転機を作る(=“気づき”の設計)
ここで「ある出来事によって世界の見え方が変わる」ような体験を設計します。
例えば、「○○を知って、初めて自分が間違ってたことに気づいた」など、主人公が行動に移る動機になる「気づき」を作り込みます。
このパートがUIに組み込まれると、スクロールやクリックそのものが“物語の進行”になるんよ。
④ 行動を起こす(=サービス・商品との接点)
この気づきがあって初めて、「じゃあ試してみようかな」となる。
この流れを設計しておくことで、商品やサービスの紹介が売り込みにならずに自然な流れになるんよね。
ここで大事なのは、「主役はユーザー」であって、「商品はあくまで“サポーター”である」ってこと。
自分のブランドや商品を“導き手”として描くとバランスが良くなるで。
⑤ 結末と余韻(=信頼・共感・共有へ)
最後に「どうなったのか?」「この選択は良かったのか?」を描いて締めくくります。
ここが抜けると、「で、結局どうなったん?」ってモヤる。
逆に、しっかりとエンディングを用意しておくと、ユーザーの中でストーリーが完結して満足感が残るんよ。
このように、ナラティブ・デザインは**UX/UIという枠を超えて、「世界観に巻き込む設計」**とも言えるんです。
第5章:ナラティブ・デザインを仕事に活かす方法
ナラティブ・デザインは、単なる“おしゃれな演出”ではありません。むしろ、それはユーザーとの信頼関係を築き、共感を生むための「構造化された物語設計」です。では、実際のプロジェクトにどう応用するのか、ここでは仕事に直結する観点からお伝えしていきます。
1. クライアントヒアリングの質が変わる
ナラティブ視点でデザインを考えると、ヒアリング時の質問が自然と変わってきます。
- 「この商品・サービスの背景にあるストーリーは何ですか?」
- 「お客さんに、最終的にどんな気持ちになってもらいたいですか?」
- 「今のブランドに足りない“物語要素”は何だと思いますか?」
このような問いを投げかけることで、クライアント側も“世界観”や“共感”を軸に語り始めます。すると、提案が単なる機能紹介ではなく「物語の翻訳」になっていくんです。
2. プレゼン資料にも“ストーリーライン”を
例えばLPの構成を提案するときも、「ファーストビュー → ベネフィット紹介 → お客様の声 → クロージングCTA」という流れを“ドラマチックな起承転結”として捉えるようになります。
僕はよくプレゼンでこんな説明をするんよ:
「このLPは、ユーザーの不安を“序章”として提示し、製品との出会いを“運命の出会い”として描いています。そして、体験談を“転機”にして、最後に“共鳴と決断”へ導く流れです。」
── これ、響き方がまったく違うよね。
数字や理屈だけじゃなく、“情緒と物語”を伝えることで、クライアントの意思決定が格段にスムーズになります。
3. ブランディングの軸が明確になる
ナラティブ・デザインは、「どんな物語をユーザーに語りかけたいのか?」という問いから始まります。だからこそ、トンマナやビジュアル、UX全体の設計に一貫性が出やすいんよ。
たとえば、同じ商品でも「職人のこだわりを伝えたいブランド」と「女性の憧れを引き出したいブランド」では、まったく異なるナラティブが必要です。その設計が甘いと、どれだけ優れたUIをつくっても、ユーザーの心には刺さらん。
4. コピーやトーンにも一貫性が出る
ナラティブが定まると、見出しやボタンの文言ひとつとっても、“人格”が宿るようになります。ブランドが人なら、どんな声で、どんな言葉で話しかけるのか──その「語り口」を統一するだけで、ブランド体験に深みが出るんです。
終章:ナラティブ・デザインは、未来の共感設計
AIが台頭し、誰もがそれっぽいデザインを作れる時代になってきました。けどな、そういう時代やからこそ「人間が物語を紡げるかどうか」が価値になる。
ナラティブ・デザインは、単なる演出でも技術でもない。
それは「誰かの人生にそっと寄り添う」設計。
デザインは情報設計であると同時に、感情の設計やけんね。
「見せる」ではなく「語る」
「使わせる」ではなく「共感させる」
この視点を持つことで、あらゆるプロジェクトがもっと深く、もっと意味のあるものになっていく。
あなたが今抱えている“伝わらないモヤモヤ”や、“世界観が曖昧なブランド”──その正体、もしかしたら「ナラティブがない」ことかもしれません。
だからこそ、僕は声を大にして言いたい。
“UX/UIを超えて、物語を設計せよ。”
💬ナラティブ設計、相談してみませんか?
「ナラティブ・デザインを取り入れてみたいけど、どこから手をつけたらいいのかわからない」
「今のブランドやLPが、なんだか平板でイマイチ伝わらない…」
そんなお悩みをお持ちの方へ。
まずは気軽にこちらのフォームからご相談ください👇
👉 https://docs.google.com/forms/d/1fptnXOg0HCzFWKg1Xldgi_IRyiHv3vwV-5uLtUMFA1s/edit



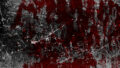
コメント