第1章:なぜ“器用貧乏”のままだと生き残れないのか?
僕はこれまで、20年以上デザインの仕事をしてきた。
グラフィック、WEB、LP、UI/UX、ディレクション、ブランディング…いろんな領域に携わってきたからこそ、よく言われてきたのが「なんでもできる人ですね」という言葉。
もちろん嬉しい。
でもね、同時にこうも感じてきた。
「なんでもできるけど、何者でもない」って状態になってないか?
いわゆる“器用貧乏”ってやつだ。
ある程度なんでもできるスキルがあるのに、指名されない。依頼が来ない。誰にも「この人じゃなきゃ」って思われない。
その原因は、実は“スキル不足”じゃなくて、“思想不在”にあるんじゃないかって気づいた。
第2章:スキル時代から思想時代へ
少し前まで、デザイナーって「技術職」だった。
PhotoshopやIllustrator、Figmaを自在に使える人、構成やレイアウトが美しい人が重宝されていた。
でも今や、テンプレートもAIも増えて、一定のクオリティは誰でも出せる時代になった。
つまり、「上手いだけの人」は代替可能になったってこと。
ここで必要になってくるのが、「なぜそうデザインするのか?」を語れる力。
いわば、「思想」や「哲学」だ。
同じスキルを持っていても、思想を持つ人は“選ばれる”。
思想がない人は、スキルで消耗戦に巻き込まれる。
思想って言うと難しく感じるかもしれないけど、要は「自分は何を大切にしているか」「どんな世界を作りたいか」っていう軸のこと。
第3章:思想とは「過去」と「未来」の掛け算
じゃあ、その“思想”ってどうやって作るの?って話になるよね。
僕の答えはシンプルで、
「自分の過去」と「これからの社会への仮説」を掛け合わせること。
- どんな人生を歩んできたか
- 何に怒り、何に感動してきたか
- どんな人と関わり、何を学んだか
ここに、“これからの時代はこうなる”という仮説を加えると、独自の視点が生まれる。
たとえば僕の場合、
「クライアントに振り回されるデザイナーを減らしたい」という想いが強い。
だから、「思想を持ったデザイナーは、受け身から脱し、戦略的に選ばれる存在になれる」という仮説に基づいて動いている。
これが、僕の思想のベース。
第4章:思想は“言語化”して初めて伝わる
ここ、めちゃくちゃ大事なポイント。
どんなに熱い想いがあっても、言葉にしなきゃ伝わらない。
思想は、発信して初めて“価値”になる。
- ポートフォリオの冒頭に思想を書く
- SNSで日々、思考の断片を発信する
- ブログやnoteで、仮説と実践を記録する
これらを通して、「思想があるデザイナー」として認識されていく。
そして、面白いことに──
思想を発信すればするほど、「思想に共鳴した人」が依頼してくれるようになる。
結果的に、変なクライアントが来なくなる(笑)
僕らは“誰にでも好かれる”必要はない。
“思想に共鳴する人”に深く刺さる存在になれば、それで十分。
第5章:なぜ“器用貧乏”は評価されにくいのか?
ここで、よく言われる“器用貧乏”という言葉について、少し深掘りしておきたいと思います。
この言葉、聞いたことがある方も多いと思いますが、実際のところなぜ“器用”なのに“貧乏”になってしまうのでしょうか。
実際、僕もかつては「全部できるデザイナー」であることが強みだと思っていました。
Webもグラフィックも、印刷も動画も、ディレクションも講師もできる。なのに、なぜか引き合いが弱い。実力はあるのに、なぜか評価がされない。
結論から言うと、専門性が伝わらないからです。
人間の脳は、“わかりやすいタグ”で他人を分類します。
「ロゴに強い人」「Webデザイナー」「イラストが上手い人」…そういったラベルがないと、どれだけ高いスキルを持っていても“印象に残らない”んです。
この現象は「認知負荷」とも関係しています。
「何でもできる」は、脳にとって処理しきれない曖昧な情報。結果、記憶に残らない。つまり選ばれない。
いくら実力があっても、「この人は〇〇の人だ」と思い出してもらえなければ意味がない。
だから僕は、自分の中で**“思想”を軸に据える**ことにしました。
第6章:“思想”という最強のタグを持て
じゃあ「思想」ってなんやねん、って話ですよね。
ここで言う思想は、「自分なりの世界の見方・価値判断・信念」みたいなものです。
例えば僕なら、
- デザインは“思想を可視化する行為”だと思っている。
- デザインは“武器”であり、“言語”であり、“戦略”だと信じている。
- クライアントの奥にある“意図”や“世界観”まで引き出して可視化するのがプロの仕事だ、という哲学がある。
この思想を軸にして発信したら、共鳴してくれる人が明確に現れるようになりました。
むしろ「この思想が欲しかったんです」と言ってくれるクライアントまで現れた。
つまり、思想はラベル以上の“磁力”になるんです。
特に今の時代、誰でもデザインができるようになってきています。
テンプレート、AI、ノーコード…そういった“量産ツール”では補えない「思想性」が、デザイナーに求められるようになってきた。
あなたの頭の中にある「当たり前」は、実は誰かにとっての“唯一無二”なんです。
それを言語化して、タグにして、ラベル化しておく。それだけで勝負は大きく変わります。
第7章:器用さを捨てず、“思想”で武器化する方法
ここまで読んで、「じゃあ器用なスキルたちは無駄だったのか?」と思った方。
安心してください、それはむしろ最高の素材です。
ポイントは、器用なスキルを“思想のもとに束ねる”ことです。
いくつもあるスキルや経験を「ただ持っている」だけでは伝わらない。
けれど、「思想という幹」さえあれば、そこから枝として繋げていける。
たとえば、
- 「世界観を見抜いて整える」という思想があれば、ロゴ、Web、UI、広告…どれも“同じ視点”で統一感ある提案ができる。
- 「抽象と具体の橋渡しをする」という思想があれば、ディレクションも講師もブランディング設計も、全部一本の線で語れる。
つまり、“器用”さは、“思想”によって武器化できるんです。
そしてこの思想を「発信」することで、自分の価値を見つけてくれる人が必ず現れます。
第8章:これからのデザイナーの未来地図──“思想持ち”が切り開く世界
これからの時代、テクノロジーはますます進化し、AIや自動生成ツールの発達によって「綺麗に整ったデザイン」だけでは差別化できなくなっていくでしょう。
すでにFigmaやCanva、さらにはAdobe Expressなどのツールを使えば、テンプレートに沿ってある程度見栄えのするデザインは誰でも作れてしまう時代です。
じゃあ、我々デザイナーに何が求められるのか。
それは「問いを立てられる人間であること」だと、僕は思います。
どんな時代にも、
- なぜそれを作るのか?
- 誰のために、どんな感情や行動を生み出すために?
- 何を信じ、どんな世界をつくりたいのか?
──こうした“思想”がある人が、結果として選ばれ、信頼されていきます。
思想を持ち、戦略を描き、表現を通して社会に関わる。
それがこれからの「本物のデザイナー」の姿やと思うんよ。
表層的な「オシャレさ」で勝負する時代は、もう終わりに差しかかってる。
これからの時代に輝くのは、「思想×美意識×構造理解」を併せ持つデザイナー。
つまり、“自分というレンズで世界を再構築できる人”です。
終わりに:器用貧乏から思想持ちへの第一歩は、“選ぶ”こと
器用貧乏な状態って、「全部できるけど、何が得意か自分でもよく分かってない」ってやつやと思うんよ。
でもね、それって裏返せば、“全部ある程度できる”っていう強みでもある。
だからこそ、自分の思想と向き合って、「何を選び取るか」が大事なんやと思います。
完璧じゃなくていい。尖ってなくてもいい。
でも、「自分はこういう人間で、こういう世界をつくりたいんや」って、ちゃんと言えるようになること。
それが、器用貧乏を脱する最大の戦略であり、思想持ちになるための入口。
僕もまだまだその途中やけど、一緒にその道を進んでいける仲間が増えたら嬉しいなって、ほんまに思ってます。
デザインにお悩みの方へ
もし今、「自分のデザインに自信が持てない」「思想をどう表現していいか分からない」そんな悩みを抱えているなら、ぜひ一度ご相談ください。
あなたの中に眠る“思想の芽”を、共に言語化・可視化するお手伝いができるかもしれません。
▼こちらからご相談いただけます
👉 デザイン相談フォームはこちら

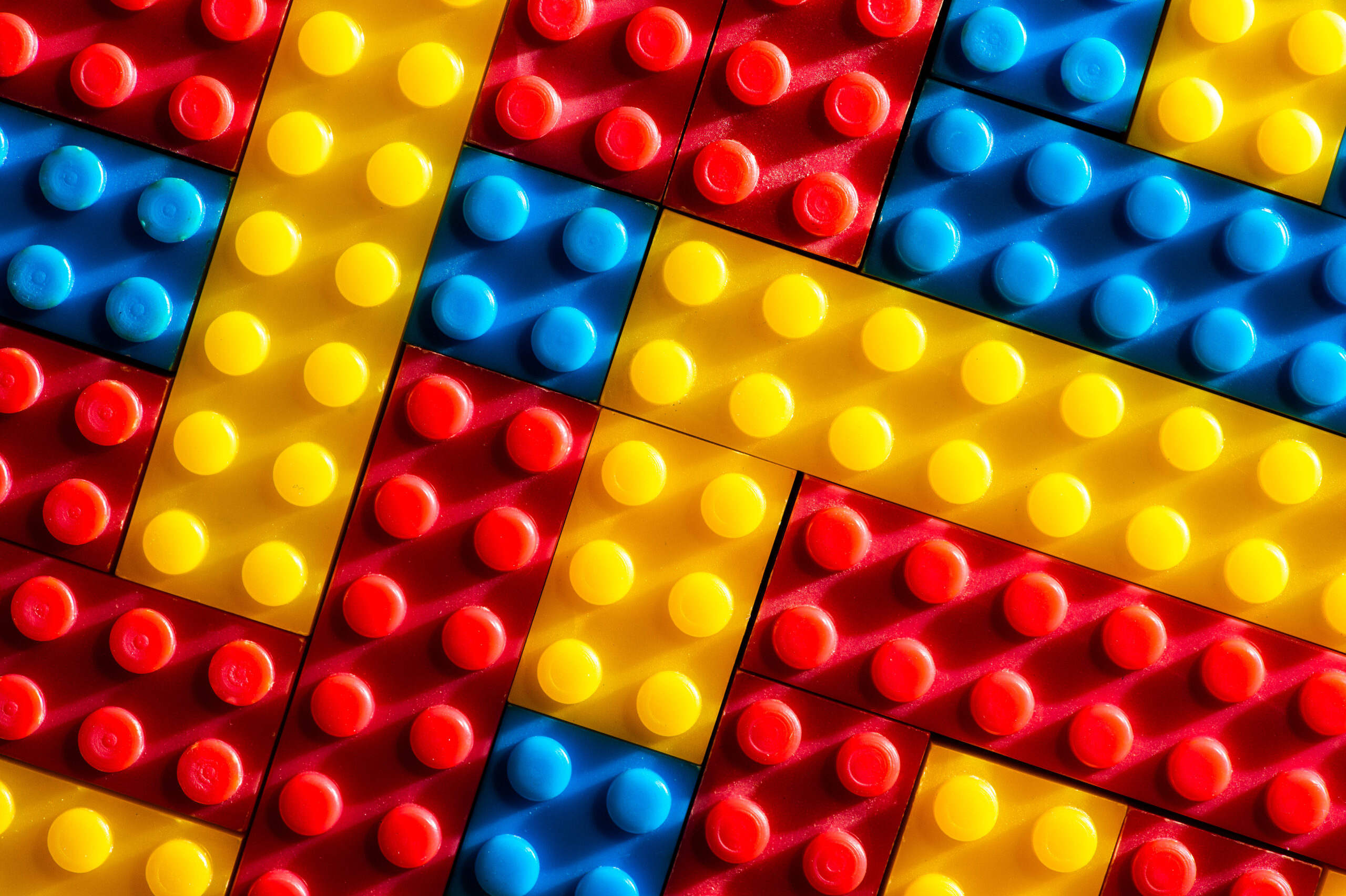


コメント