第1章:「デザインができる」だけじゃ、足りなくなった時代
最近、よく耳にしませんか?
「AIにデザインを任せられる時代になってきた」とか
「デザイナーはオワコン」なんて声。
でも、僕は思うんです。
**むしろ、これからが“本当の意味でのデザイナーの時代”**なんじゃないかって。
理由はシンプルで、
「誰でもつくれる」時代だからこそ、“考えられる人”に価値が集中するから。
第2章:量産型から、思考型へ──デザイナーの変化
昔:つくれる人が重宝された
PhotoshopやIllustratorを自在に操れる。
複雑なレイアウトやアニメーションを再現できる。
そんな「手が動く人」は、確かに重宝されました。
でもいまは、Canvaもある。Figmaもある。AIもある。
つまり──
“つくれる”こと自体の価値が下がってきた。
今:考えられる人が求められている
今必要なのは、「何を、なぜ、どうつくるか?」を思考できるデザイナー。
- 誰に届けたいのか?
- なぜこの配色なのか?
- なぜこの情報設計なのか?
そうやって背景と目的をセットで考えられる人が、真のプロフェッショナルとして選ばれる時代に変わってきてます。
広島弁ちょっと挟むと…
昔は「とにかく手ぇ早いヤツ」が重宝されとったんじゃけど、
今は「ちゃんと考えられるヤツ」じゃないと生き残れんようになっとるんよね。
第3章:なぜ“考えられる人”が強いのか?
「考える」といっても、ただ難しいことをこねくり回すって話じゃありません。
“考えられる”とは、
「意図を持って、意味のあるデザインを構築できる」ってこと。
そしてこのスキルは、以下のような場面で特に強みを発揮します:
● クライアントワークでの提案力
「いい感じのデザインにしてください」と言われたとき、
“ただ作る”だけではなく、“なぜそうするのか”まで言語化して提案できる人は、信頼されます。
● チームとの連携
エンジニアやマーケターと連携する場面でも、
「ただの見た目」ではなく「設計思考」があるとコミュニケーションが圧倒的にスムーズになります。
● 差別化
見た目だけのデザインは、AIでもできるようになりました。
でも“背景を読み取り、戦略を踏まえて”アウトプットできる人は、まだまだ少数派。
つまり、“考える力”こそが、これからの差別化の鍵になるってこと。
【1/3】終了!
続けて【2/3】にいくけん、まかしとき!
続きいくよ、【2/3】スタートじゃ!
第4章:“考えられる人”になるために必要な視点
じゃあ、どうすれば「考えられるデザイナー」になれるんか?
ここでは、僕自身が意識している5つの視点を紹介します。
① 「誰のために?」を最初に問う
デザインは、相手がいて初めて成立します。
だからまず「誰のためにこのデザインをつくるのか?」を問い直すことが大前提。
- ユーザーの性別・年齢・悩み・好みは?
- その人が“見たい情報”って何?
- “どこで”見る?(スマホ?PC?電車の中?)
こうした「ユーザーの状況」を想像する力が、“考える”の第一歩。
② 設計から逆算する
「どんな見た目にしよう?」より先に、
「どんな行動を起こしてほしいか?」から考える癖をつける。
- 資料請求してほしい
- 商品購入してほしい
- とにかく最後まで読んでほしい
この目的がハッキリしていれば、配色も構成も自然と決まってきます。
これが設計思考の基本です。
③ 言語化する力を育てる
我々デザイナーって、「なんとなく良い」「雰囲気が好き」で作ることも多いですよね。
でも、クライアントやチームに共有する時は、それじゃ通じん。
“感覚を、言葉に変換する力”──これがあると一気に信頼が高まります。
④ 引き算の美学を身につける
詰め込みすぎたデザイン、見たことないですか?
“余白が怖い病”とも言われたりしますけど、
引き算できる人は、「何を見せたいか」が明確な人です。
これは、思考の筋力でもある。
⑤ 世界観で魅せる
ビジュアル・コピー・空気感。
「なんか好き」って思わせるのは、世界観の力です。
考える力がある人ほど、“自分の軸”を持ち、
“自分なりの答え”で魅せることができます。
第5章:「つくれる」だけでは戦えない理由
昔の話ですが、僕がまだ駆け出しの頃、
「言われた通りに作れる=優秀」と思ってた時期がありました。
でもある日、クライアントから言われたんです。
「で?このデザイン、誰に響くの?」
そのとき、自分、何も答えられんかった。
ただ綺麗に見せただけだったから。
「言われたものをつくる」だけでは、AIと変わらない
AIは、すでにあるデータから「それっぽいもの」を生成できます。
でも“人の本音”とか“矛盾を含んだ現実”って、AIにはまだわからん。
僕らに求められるのは、
- 文脈を読む力
- 感情を察する力
- 言語にならないニュアンスを読み取る力
つまり、“人間の複雑さ”に寄り添うセンスなんですよね。
だから、「考えられる人」が最後に選ばれる
僕の周りでも、
「技術がすごい人」より「思考が深い人」のほうが、仕事が絶えません。
考えられる人は、
- クライアントの要望を本質で捉え
- その課題に対して答えを導き出し
- “形”に落とし込んで、言語でも説明できる
…ここまでできると、もう最強です。
【2/3】ここまで!
いよいよ次で完結編【3/3】じゃけぇ、お楽しみに!
おまたせ!ラスト【3/3】いくよ。最後までしっかりまとめて完走するけんね!
第6章:「考える力」を武器にする方法
じゃあ、どうすれば“考えられるデザイナー”になれるのか。
これは才能やセンスじゃなく、意識と訓練で鍛えられる力です。
以下は、僕自身が実践して効果があった方法を紹介します。
● 日常を「なぜ」で見るクセをつける
街中のポスターや広告を見たとき、
ただ「オシャレ〜」で終わらせずにこう問いかけてみてください:
- なぜこの配色なんだろう?
- どこがアイキャッチになってる?
- 誰に向けてつくってるのか?
これを繰り返すと、どんどん“構造”が見えてくるようになります。
● 他ジャンルの“考え方”を吸収する
マーケティング、心理学、行動経済学、ストーリーテリング…。
こうした“思考系”の知識をインプットすると、
自分のデザインにも「言葉で語れる理由」が増えていきます。
僕も心理学とか脳科学とか、よう勉強したけど、
めっちゃデザインに応用できるんよ。ホンマに。
● 壁打ちの相手を持つ
自分の考えをアウトプットすることで初めて、
「どれだけ考えてなかったか」がわかります(笑)
信頼できる相手と、
「なぜこの構成にしたのか?」
「このターゲットに伝わると思う?」といった壁打ちをするだけで、
思考はめちゃくちゃ鍛えられます。
第7章:未来を見据える──“戦略的デザイナー”という進化形
僕が目指しているのは、**「戦略を組み立てられるデザイナー」**です。
見た目のデザインだけじゃなくて、
- ブランドの方向性
- ターゲットの心理
- コンテンツの配置
- 導線設計
- ビジネスモデル全体
ここまで関われるようになると、クライアントの右腕になれます。
“見える世界”が変わると、仕事の単価も変わる
「ただのデザイナー」だと1枚3万円でも高いと言われる。
でも「考えられるデザイナー」なら、1枚30万円の提案もできる。
違いは、**“何を見ているか”と“どこまで考えているか”**です。
あなたの思考は、最大のクリエイティブ資産
いま、ChatGPTや生成AIが注目されてる時代だからこそ、
「考える力」っていう人間の本質的なスキルが見直されてます。
デザインも同じ。
つくれるだけじゃダメ。考えて、導き出して、形にする。
これが、これからのデザイナーに必要なものなんだと思います。
まとめ:これからの時代を生き抜くデザイナーとは?
- つくれるだけじゃなく、考えられること
- クライアントやユーザーの意図や感情に寄り添えること
- デザインを言葉で説明できること
- 他分野の知識を吸収し、俯瞰して設計できること
これらを少しずつでも意識していけば、
間違いなく“選ばれるデザイナー”に進化していけます。
デザインの相談、してみませんか?
もしあなたがいま、
- 自分のデザインがなんとなく“浅い”気がしている
- 言語化に自信がない
- もっと“選ばれる存在”になりたい
そんな風に思っているなら、ぜひ一度ご相談ください。
僕が全力で壁打ちさせていただきます。
👇こちらからお気軽にどうぞ!
デザインの相談はこちら

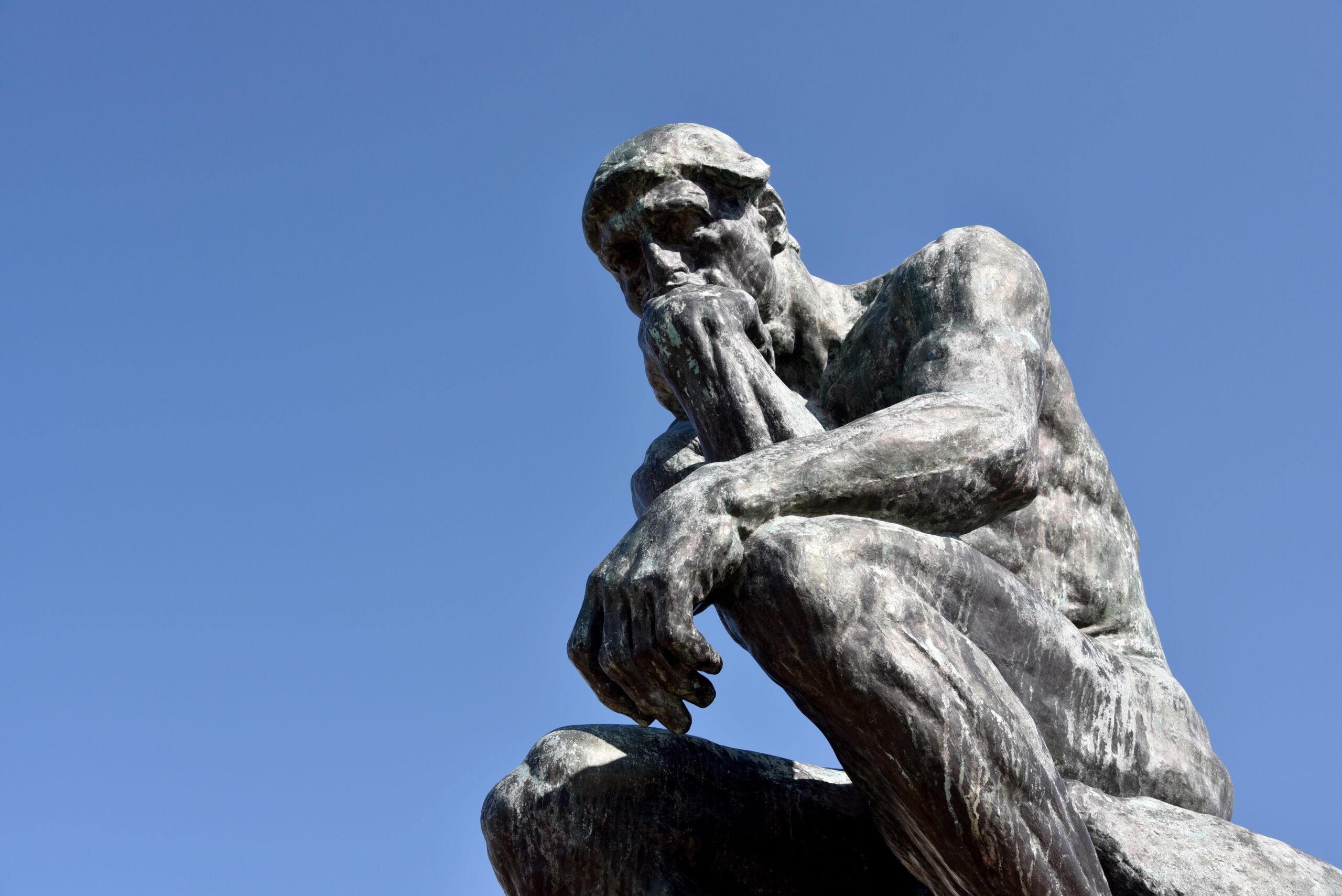


コメント