はじめに:「なんかいい感じ」の正体って?
デザインの現場で、よく耳にするフレーズがあります。
「このデザイン、“なんかいい感じ”だね!」
褒め言葉としても嬉しいし、悪くはないんだけど……。 現場で本当に役立つのは、「なぜいいのか」「どうして良く見えるのか」を構造的に説明できる力です。
それができるようになると、
- 自分で納得感を持ってブラッシュアップできる
- 他人に提案する際、説得力が段違いになる
- チームやクライアントとの認識ズレが減る
など、デザイン力全体が跳ね上がります。
この記事では、「“なんとなくいい感じ”」を言語化するための視点をお伝えします。
1. デザインを「感覚」から「構造」で見る
まず最初に意識しておきたいのが、デザインには構造があるということ。
構造とはつまり、
- 情報の整理(階層、重要度)
- 視線誘導の流れ
- 配置とリズム
- 配色のバランス
- フォントと文字組み
- コンポーネントの統一感
など、論理的に分解できる“設計”のことです。
これは「センス」で片付けられがちですが、実は再現性があるもの。一流のデザイナーほど、構造を明確に意識しています。
2. 「構造」を読み解くための視点
以下のような観点でデザインを見てみましょう。
■ ① 目的から考える
「なんのためにこのデザインがあるのか?」 → サービスの紹介?購買の促進?信頼感の演出?
■ ② 誰に向けたものか(ターゲット)
Z世代向け?経営者?子育て中の主婦? → 価値観・視覚トーンが変わってくる
■ ③ 視線の流れ
視線がどこからどこへ流れていく? → フォーカルポイント(目立たせるべき場所)が機能してる?
■ ④ 情報の階層構造
重要なものがちゃんと大きく、目立っているか? → タイトル・小見出し・本文の順にわかりやすいか?
■ ⑤ 配色と余白
色が役割に沿って使われてる? → 強調・抑制・導線などが整理されている?
3. 「良いデザイン」を言語化する例
例として、あるバナー広告を見て「なんかいい」と感じたとします。
その“いい感じ”を言語化すると:
- 強調すべきワードが中央に配置されていて目に入る
- 配色が限定されていて、情報が散らからない
- フォントがターゲット(Z世代)に親和性のあるテイスト
- アイキャッチとなるイラスト・写真がしっかり機能
- コンポーネントに統一感があり、全体が整理されている
→ これらを見抜いて、ひとつずつ言葉にしていく。
この練習を繰り返すことで、言語化筋が育ちます。
4. フレームワークで構造化する
「良いデザイン」を構造的に捉えるフレームワークも有効です。
🔷 VSU法(Visual・Structure・Usability)
- Visual(視覚的な魅力)…色・フォント・写真など
- Structure(構造)…情報の流れ、視線誘導、余白設計
- Usability(使いやすさ)…操作性、読みやすさ
この3つに分解するだけで、漠然とした「なんかいい」がぐっと具体化されます。
5. 言語化できると「自分の作品」も変わる
言語化は、他人のデザインに対してだけじゃなく、 自分のデザインに対しても効果絶大です。
「なんとなく違和感がある…」 ↓ 「構造を見直してみよう」 ↓ 「視線誘導の流れが悪い?余白が詰まってる?」
と、原因を構造的に探れるようになります。
こうなると、
- デザインの迷いが減る
- 「こっちがいい」理由を語れる
- 説得力のあるプレゼンができる
=スキルも、評価も、説得力も上がる!
6. 「言語化の練習」は誰でもできる
最後に、「どうやって鍛えればいいの?」という人向けにおすすめの練習法を:
📝 おすすめのトレーニング
- 好きなデザインをスクショで集める(Pinterestなど)
- 「なぜ好きか?」を5つの視点で言語化して書き出す
- 友達やAIに説明してみる(アウトプット)
最初はうまく言葉が出てこなくても大丈夫。 「構造」と「目的」に意識を向けるだけでも視野が広がっていきます。
おわりに:「なんとなく」は、ちゃんと説明できる
「センスって、持ってる人だけのものじゃない?」 そう思っていたら、もったいない。
センスは「構造×経験」で鍛えられます。
“なんとなく”を“なるほど”に変える。 それが、デザインを武器に変える第一歩。
💬 ご相談はこちら
デザインの構造や言語化について「もっと知りたい!」「添削してほしい!」という方は、 お気軽にこちらからご相談ください👇


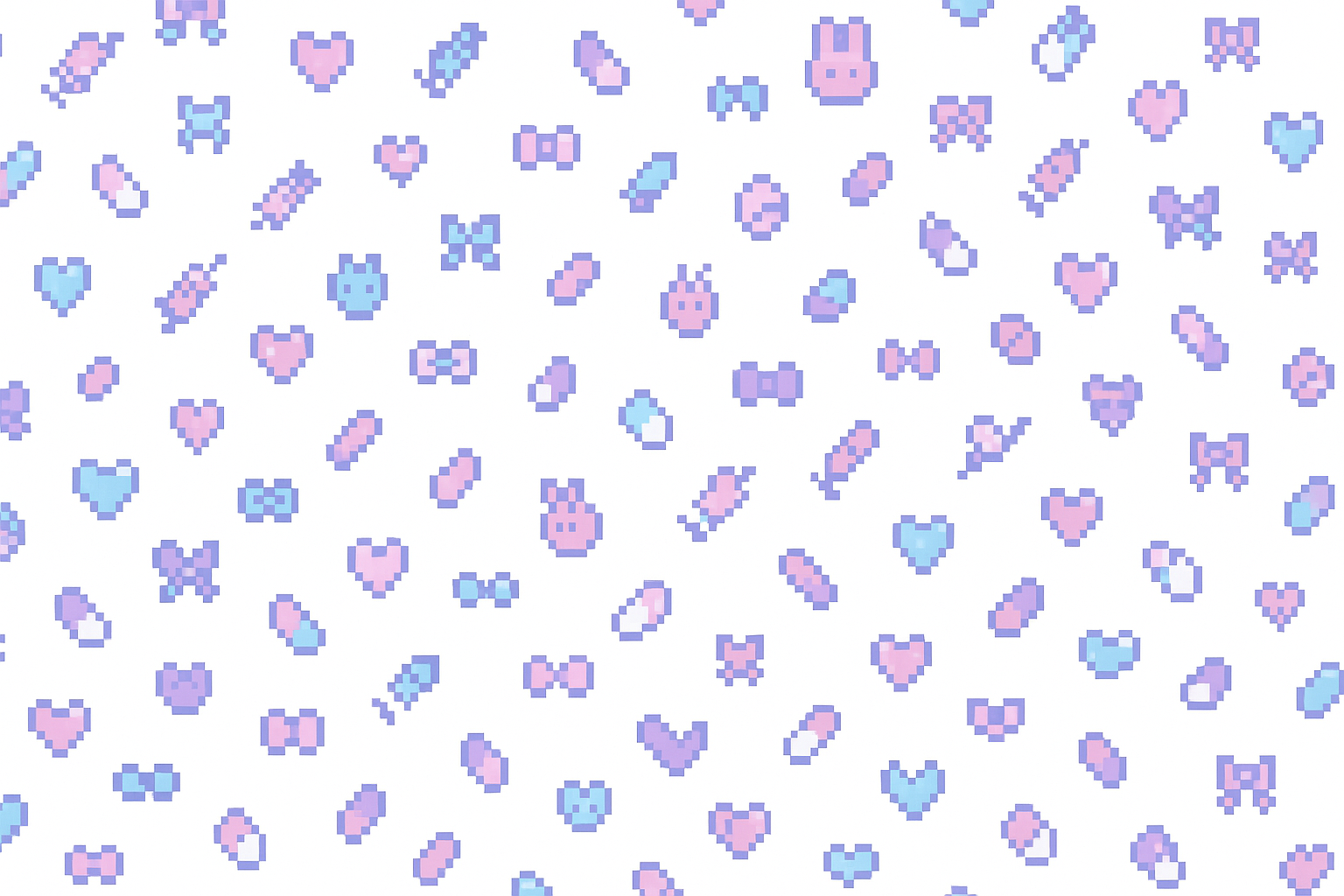

コメント