はじめに
「ユーザー視点を大切にしましょう」──デザインに関わる人なら、一度は耳にしたことがあるフレーズだと思います。
でも、実際に作業に落とし込むと「結局、何を基準に判断すればいいんだろう?」と迷った経験はありませんか?
僕自身、アートディレクションやUIデザインの現場で「ユーザー視点」という言葉を何度も使ってきましたが、それが“曖昧な魔法の言葉”として扱われてしまうケースをよく目にします。
そこで今回は、ユーザー視点を「見る」「触る」「感じる」という3つの階層に分けて整理し、実際のデザインワークにどう活かすのかを解説します。
第1章:そもそも“ユーザー視点”とは何か?
ユーザー視点という言葉は便利ですが、非常に抽象的です。人によっては「自分がユーザーだったらどう感じるか」を基準にしてしまうこともあります。
しかし、ここに落とし穴があります。
- デザイナーの自分視点 ≠ 実際のユーザー視点
- クライアントの意見 ≠ ユーザーの意見
つまり、“自分が思うユーザー目線”は、しばしば独りよがりな想像にすぎないのです。
本当に必要なのは、ユーザーが「どの段階で」「何を」「どう感じるか」を体系的に分けて捉えることです。
そこで僕は、ユーザー体験を「見る」「触る」「感じる」という3つの目線に分解して考えることを提案します。
第2章:“見る”目線 ─ ビジュアルとしての第一印象
ユーザーの体験はまず「目から入る情報」で始まります。
これはWebサイトでもアプリでも広告バナーでも同じです。
- レイアウトのわかりやすさ
- 文字の読みやすさ
- 色や写真の印象
これらはすべて「見る」段階での判断材料です。ユーザーは、数秒以内に「自分に関係があるか・ないか」を無意識に判断します。
例えば、文字が小さすぎたり色のコントラストが弱すぎると「読む前に離脱」されます。
逆に、強調すべき部分が明確で、視線が自然に流れる設計になっていれば「続きを見てみよう」と感じてもらえます。
“見る目線”を制するものは、ユーザー体験の入口を制する──これは間違いありません。
第3章:“触る”目線 ─ 操作としての体験
次に重要なのが「触る」という目線です。ここで言う“触る”とは、UIの操作やインタラクションを通じて得られる体験のことです。
- ボタンが押しやすい位置にあるか?
- スクロールやスワイプで迷わないか?
- リンク先に行ったあと、戻りやすいか?
ユーザーは直感的に「操作しやすい・しにくい」を判断します。
特にモバイル環境では、指の可動域や片手操作のしやすさなど、細かい要素が体験の快適さを左右します。
広島弁で言えば「押しにくいボタンじゃけぇ、使う気にならん」ってことです(笑)。
つまり、“触る目線”では、デザインの見た目だけでなく「実際にどう動くか」を設計する力が求められます。
第4章:“感じる”目線 ─ 感情としての体験
ユーザー体験の最終的なゴールは「どう感じてもらえるか」です。
人はデザインを見て、触ったあとに必ず「心の評価」を下します。
- 「なんか使いやすかった」
- 「デザインが洗練されていて気持ちいい」
- 「ちょっとストレスが残った」
こうした感情的な評価は、数値やKPIには直接現れにくいものの、継続利用やファン化に直結します。
例えばアプリで「操作がスムーズでストレスがない」と感じたら、ユーザーは繰り返し使うようになります。
逆に「毎回読み込みが遅い」「押し間違える」といった小さな不快感が積み重なると、二度と使ってもらえなくなるのです。
つまり、“感じる目線”を設計に取り入れることは、ユーザーを“顧客”から“ファン”へ進化させるためのカギになります。
第5章:3階層を統合したユーザー体験設計
「見る」「触る」「感じる」を別々に考えるのではなく、ひとつの流れとして統合することが重要です。
- 見る ─ 第一印象で関心を引く
- 触る ─ 操作で迷わせずストレスを排除する
- 感じる ─ 心地よさや安心感でファン化させる
この3階層は「順番に積み上がっていく」ように機能します。
見た目が良くても触りにくければ不満が残るし、操作性が良くても見た目で信頼を失えば離脱します。
よくある失敗は「見た目」だけに注力して「触りやすさ」と「感情的な心地よさ」を軽視することです。
これでは短期的な評価は得られても、長期的にはユーザーが離れていってしまいます。
第6章:実践に落とし込むためのチェックリスト
最後に、実際のデザインプロセスで使えるチェックリストを紹介します。
- 見る
- 情報の優先順位が明確か?
- 視線誘導が自然に設計されているか?
- 配色やフォントに違和感はないか?
- 触る
- ボタンやリンクは直感的に操作できるか?
- モバイル環境で指の動線は考慮されているか?
- 誤操作が起きにくい設計になっているか?
- 感じる
- スムーズに使えて気持ちよさを感じられるか?
- 安心感や信頼感を醸成する要素があるか?
- ユーザーに「また使いたい」と思わせられるか?
この3ステップを意識するだけで、デザインの質は大きく変わります。
第7章:ビジネス現場での“ユーザー視点”の活かし方
ユーザー視点の3階層(見る・触る・感じる)は、単にUI/UXの話にとどまりません。
商品開発、営業資料、ブランドコミュニケーションなど、あらゆる場面で応用できます。
例えば営業資料なら、
- 見る:最初に目を引くビジュアルやキャッチコピーで関心を引く
- 触る:スライドの流れやナビゲーションを直感的に分かりやすくする
- 感じる:最後に「信頼できそう」と思わせる安心感を残す
といった形で3階層を当てはめることが可能です。
この思考法を常に意識することで、「ただ見栄えの良いデザイン」ではなく「人を動かすデザイン」に昇華できるわけです。
まとめ:ユーザー視点は“積み木”のように積み上がる
- 見る目線で第一印象を設計する
- 触る目線で操作性を整える
- 感じる目線で感情体験をデザインする
この3階層をバラバラに考えるのではなく、一連の流れとして積み上げることが、ユーザー視点を本当に理解することにつながります。
そして大切なのは、「見る→触る→感じる」すべてを設計できるデザイナーこそ、プロとして信頼されるという点です。
どれか1つでも欠けると、ユーザーは違和感を覚え、サービスやブランド全体にマイナスの印象を持ってしまうからです。
デザイン相談はこちら
ユーザー視点を踏まえたデザイン設計についてもっと深掘りしたい方、実際の案件でのアドバイスが必要な方は、ぜひこちらからご相談ください。

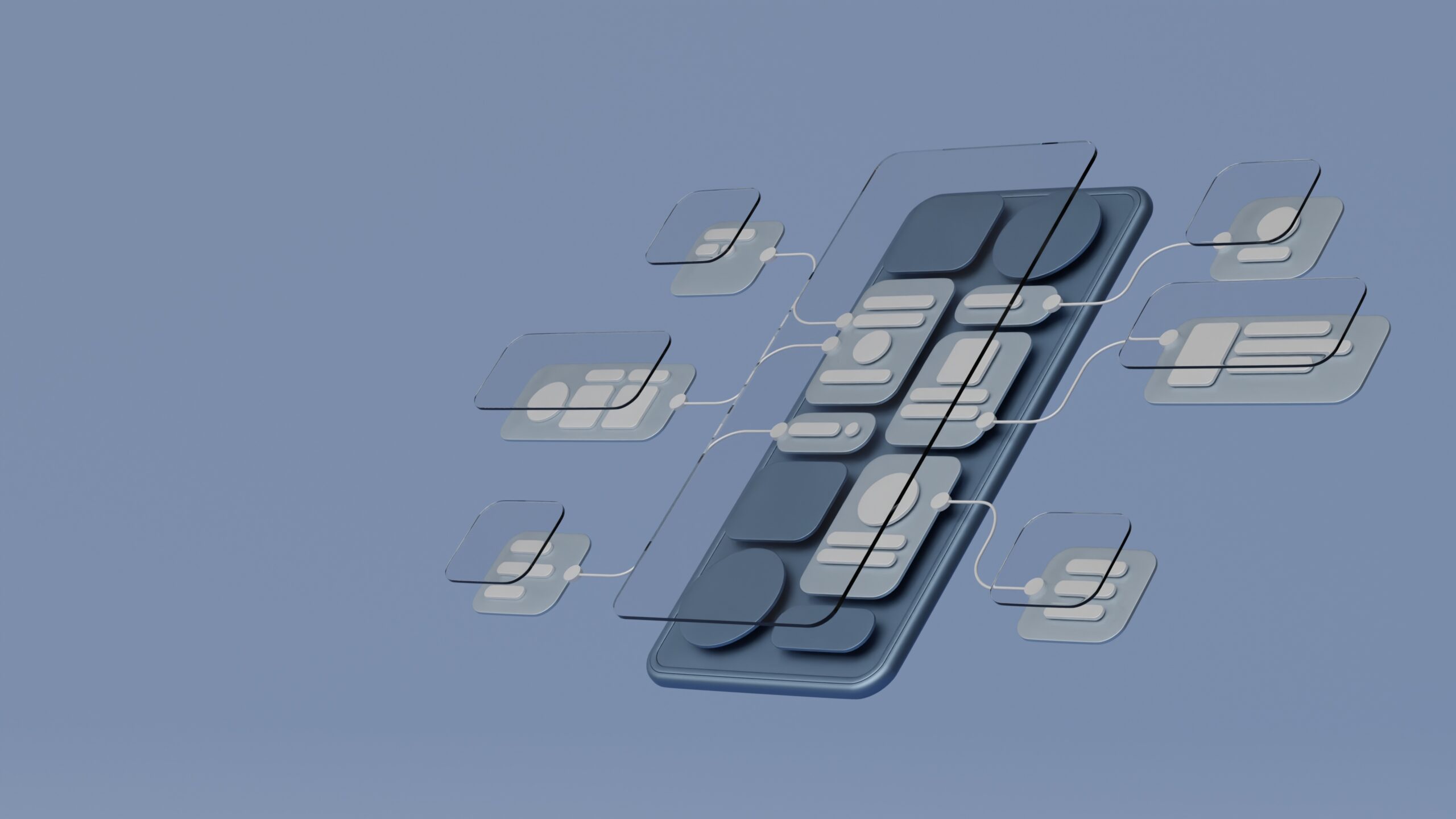


コメント