はじめに
ここ数年、AIツールが爆発的に普及し、デザイン、ライティング、データ処理、マーケティング…あらゆる領域で「AIをどう使うか?」が問われるようになりました。
ただ、多くの人が陥っているのが、**「とりあえずChatGPTを入れてみたけど、なんかイマイチ活用できていない」**という状態です。AIは“万能の魔法道具”ではなく、得意な領域ごとに適したツールを選ぶことが欠かせません。
この記事では、僕自身がデザインやライティングの現場でAIを試行錯誤してきた経験をもとに、タスク別に最適なAIツールの選び方を解説します。
「どのAIを使えばいいかわからない」
「結局、ChatGPTと他のAIの違いは何なの?」
そんな疑問をスッキリ整理して、明日から業務に活かせる活用法をまとめました。
第1章:なぜ“タスク別AI”が必要なのか?
AIの進化は凄まじいスピードで進んでいます。しかし一つのツールで全てをカバーできるわけではありません。
- ChatGPT … テキスト生成・アイデア出し・構造化が得意
- Midjourney / Stable Diffusion … ビジュアル生成・デザインのたたき台に強い
- Notion AI … ドキュメント整理・要約・チームナレッジ活用に便利
- Runway / Pika … 動画生成・モーショングラフィックに強み
- Claude … 長文理解や資料の要約で安定感あり
例えば、提案書のデザインを考えるときに「ChatGPTで画像を出そう」と思っても、画像生成は得意分野ではありません。逆にMidjourneyで「キャッチコピーを考えて」と頼んでも、言葉選びの精度は低いままです。
要するに、**「ハンマーでネジを打とうとしている状態」**になりがちなんですね。だからこそ、業務ごとに最適化されたAIを“道具箱”のように揃えて使うのが正解です。
第2章:文章系タスクで使うべきAI
1. ChatGPT(汎用テキスト生成の王様)
- 得意分野:ブログ記事、キャッチコピー、メール文面、アイデア発散
- 強み:思考整理と文章化をスピーディに行える
- 注意点:ファクトチェックは必須。特に専門領域では誤情報のリスクあり
2. Claude(長文の読解・要約に強い)
- 得意分野:議事録の要約、リサーチ資料の整理、大量テキストの理解
- 強み:文脈を壊さずに長文を扱える安定感
- 注意点:日本語対応がChatGPTより弱いケースあり
3. Notion AI(ドキュメント整理の相棒)
- 得意分野:ナレッジの分類、メモの整理、要約
- 強み:Notion上で完結するため、チームナレッジ管理に便利
- 注意点:文章生成の独創性は低め
→ 僕は実際、記事のたたき台をChatGPTで作り、長文資料の要約をClaudeに任せ、最終的にNotion AIで整理する…という流れで効率を爆上げしています。
第3章:ビジュアル系タスクで使うべきAI
1. Midjourney(高クオリティのビジュアル生成)
- 得意分野:コンセプトアート、雰囲気の提案、ビジュアルのアイデア出し
- 強み:アーティスティックで“映える”ビジュアルを出せる
- 注意点:細かい修正が難しく、商用利用時は著作権に注意
2. Stable Diffusion(カスタマイズ性の高さ)
- 得意分野:思い通りのイラスト生成、細かい調整
- 強み:オープンソースで自由度が高い
- 注意点:環境構築に知識が必要、学習コストが高い
3. Canva AI(手軽さが売り)
- 得意分野:SNSバナー、資料用の画像生成
- 強み:非デザイナーでも直感的に扱える
- 注意点:表現力はMidjourneyに劣る
→ 僕の使い方としては、デザインの初期アイデアをMidjourneyで出し、実務の調整や仕上げは自分でFigmaやIllustratorでやる、という流れが一番相性が良かったです。
第4章:動画・モーション系タスクで使うべきAI
1. Runway(次世代の動画編集AI)
- 得意分野:動画編集、BGM自動生成、グリーンバック除去
- 強み:映像制作の“手間がかかる部分”を一気に短縮できる
- 注意点:高解像度出力は有料、まだプロ用としては粗さが残る
2. Pika Labs(テキスト→動画生成の注目株)
- 得意分野:短尺のアニメーションやモーショングラフィック
- 強み:プロンプト入力だけで動きのあるビジュアルを生成できる
- 注意点:生成結果のコントロールは難しく、使いこなしには試行錯誤が必要
3. Kaiber(既存素材のアニメーション化)
- 得意分野:イラストや写真を動画に変換
- 強み:音楽PVやSNS向け動画に強い
- 注意点:リアル系よりもアート系表現向き
→ 僕はデザイン提案のときに、バナーの世界観をKaiberで動画化してクライアントに見せることがあります。これだけで「おお!」とリアクションが大きく変わるので、AI動画の威力を実感しています。
第5章:業務効率化タスクで使うべきAI
1. Perplexity AI(調査・リサーチの即戦力)
- 得意分野:検索+要約
- 強み:最新情報を調べながら回答できる
- 注意点:情報源を必ず確認する必要あり
2. ChatGPT Code Interpreter(データ処理の強い味方)
- 得意分野:エクセル処理、グラフ作成、簡単なスクリプト生成
- 強み:非エンジニアでもデータ分析が可能
- 注意点:複雑なプログラムは得意ではない
3. Jasper(マーケティング特化型AI)
- 得意分野:広告コピー、SNS投稿、ランディングページ文章
- 強み:マーケティング文脈での言葉選びが強い
- 注意点:日本語はやや不自然な場合あり
→ 実際、僕はリサーチをPerplexity、データ整理をChatGPT Code Interpreter、マーケ施策の文章はJasperというふうに役割分担して活用しています。
第6章:AIツールをどう“設計”して使うか
ここまで見てきたように、AIツールにはそれぞれ得意不得意があります。大事なのは「どの場面でどのAIを使うか?」を設計しておくことです。
1. アイデア発散 → ChatGPT・Midjourney
2. 情報整理 → Claude・Notion AI
3. 提案資料・ビジュアル化 → Midjourney・Canva AI
4. 動画化 → Runway・Kaiber
5. リサーチ・マーケ活用 → Perplexity・Jasper
このように、業務フローごとにAIを割り振ると“道具箱”のように使いやすくなります。
つまり、AIを使いこなすコツは「万能を求める」のではなく、最適なツールを“つなぎ合わせて”使うことなんです。
第7章:AIツール選びで絶対に外せないポイント
ここまで様々なAIを紹介してきましたが、最終的に大切なのは「何を目的にするか」です。AIツールは無数にありますが、以下の3つを押さえるだけで選びやすくなります。
- 目的適合性(タスクとツールが合っているか)
例:文章生成をデザインAIに任せても効率は悪い。役割を間違えると成果が出にくい。 - 操作性(自分やチームが使いやすいか)
例:高性能でも操作が複雑だと現場で使われない。UIやワークフローに合うかが重要。 - 再現性(同じ品質を安定して出せるか)
例:毎回バラバラのアウトプットしか出ないツールは“仕事道具”としては心もとない。
まとめ:AIは“使い分け”がすべて
AI時代の勝ち方は「万能な1つを探すこと」ではなく、最適なツールを組み合わせることです。ChatGPTだけに頼るのではなく、ClaudeやMidjourney、Perplexityなどを役割に応じて配置する。これが現場で差を生む一番のポイントだと僕は思っています。
デザイナーでもマーケターでもエンジニアでも、AIをどう選ぶか・どう繋ぐかで仕事の質とスピードはまるで変わってきます。だからこそ、“自分の業務に合ったAI”を冷静に選び、使い分けられることが今後ますます求められるでしょう。
デザイン相談はこちらから
もし「AIをどう業務に取り入れればいいのか?」「自社に最適なツール選びを相談したい」と思った方は、ぜひ気軽にご相談ください。僕自身、デザインだけでなくAIの活用支援も行っています。

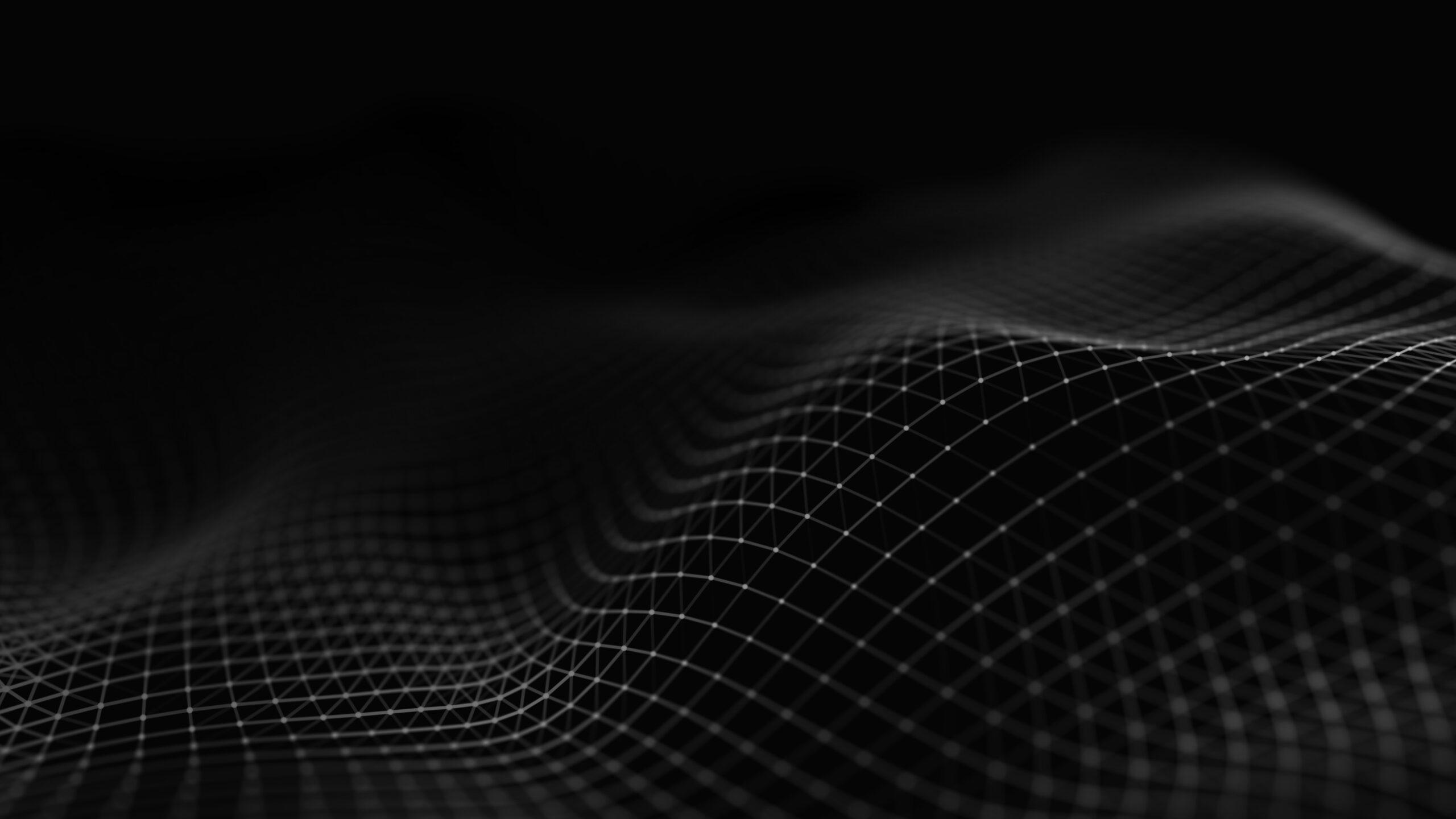


コメント